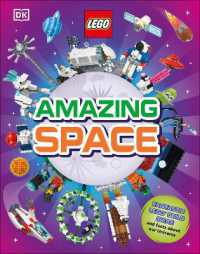内容説明
知床のことはこの男に聴け! オホーツクの海に四十余年、大船頭・大瀬初三郎はその目で見たことだけを真直ぐに語る。サケやマスについて、ヒグマやシカについて、木や草について、潮や風について、さらには流氷について……。いずれの言葉も深い。著者は二十年の歳月をかけて繰り返しこの北の地を訪れ、彼の話に耳を傾けてきた。その体験を手がかりに、世界自然遺産に登録された知床の自然を考える。
目次
第1章 春の番屋
第2章 失われた光景
第3章 夏の番屋
第4章 動物たちの森と海
第5章 秋の番屋
第6章 大船頭への道
第7章 冬の知床
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
49
私はこの作家の良い読者ではないが、作家自身が知床に小屋を持ち世界遺産登録にも影響力があったようだ。船頭の大瀬さんは現役の漁師。今は一般人の立入禁止区域でサケマス漁を営む。ヒグマ頻出地域で、かつてヒグマが出現したら殺戮していた方針だったのを、共生方針に転換させた功績で有名。本書は、大瀬さんの聞き取りだけでなく、作家の知床への思いも半分占める。世界遺産の自然を守るとは、自然を人間から隔離するのではなく、人間と共生した自然をいかに守るかという課題が、観光問題とは別に、より難題として存在することがよく分かった。2015/09/01
書の旅人
11
年内には大家と会い、さらに詳しい話をするので、来年早々には、引越し開始となるでしょう。いよいよ伊那へ本格的に移り、この地に根を降ろします。それに先駆けて、この本に出会えて良かったです。生き方は違いますが、本質は同じであり、大きく深呼吸させてもらいました。「自分が不幸だと思えば不幸になるし、嬉しいと思えば嬉しくなるものでしょ。貧しいと思えば貧しいし、これでいいと思えば幸せ」私はこの先、私が選んだこの道を歩いてゆきます。2017/12/04
gagayuta1990
2
魚が熱を持つのは、水からあげられて暴れたからではなく、死を前にした恐怖からである。 当たり前のことなのだが生は死の上にしかない。 知床が世界遺産に登録されたのは豊かな動植物の多様性と食物連鎖の成り立ちにある。 それは、人間も含めた上での食物連鎖なのだと思った。 人間とここでいうのは、その土地に生きる人達。 私のような観光客が知らない世界を教えてくれる。 観光とは、その土地を知りに行くこと。お邪魔しますという謙虚さがなければいけない。 2017/08/11
odmy
1
知床についてちょっと勉強する必要が出てきたので最初の一冊として読み始めたけれど、途中で飽きてしまった。インタビュー相手が漁師だけ(しかもたった1人)なので、話の展開が平板なのが飽きてしまった原因だと思う。もっといろんな人々の視点から知床を立体的に浮かび上がらせるような構成だと良かったのになあ。2023/07/20
Koji
1
アッサリと読めてしまいました。2014/08/24
-

- 洋書電子書籍
- Hexagonal Boron Nit…
-

- 洋書
- MONTAGNE