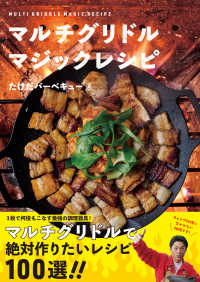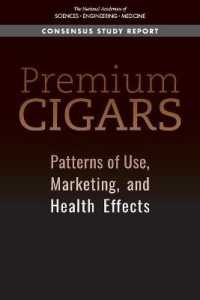内容説明
何度も郷里に引き戻されながら、江戸で学問と剣術を極めていく元司。二十五歳で清河八郎と改名、自ら塾を開くも、やがて学問の世界を離れ虎尾の会を結成、尊皇攘夷の急先鋒となっていく。しかし倒幕の機いまだ熟さず、早すぎた志士として凶刃に倒れる―悲劇の孤士の生涯をあますところなく描いた傑作長篇。
著者等紹介
藤沢周平[フジサワシュウヘイ]
昭和2(1927)年、鶴岡市に生れる。山形師範学校卒、48年「暗殺の年輪」で第69回直木賞を受賞。「白き瓶 小説長塚節」(吉川英治文学賞)など多数。平成元年、菊池寛賞受賞、6年に朝日賞、同年東京都文化賞受賞、7年、紫綬褒章受章。「藤原周平全集」(全26巻文藝春秋刊)がある。9年1月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
47
舞台は江戸、そして全国へと広がっていきます。学問と剣術を極めていく中で、やがて剣一筋となり、尊王攘夷の考えを持つようになっていくのですね。八郎が早すぎたのか、時代が遅いのか、倒幕の動きは激しいものであったように感じました。八郎はもしかしたら早すぎた志士だったのかもしれません。悲劇の孤士の生涯と言っても良いでしょう。2023/02/06
Gotoran
35
江戸時代末期の荘内藩出身の志士、横河八郎の清冽な33歳の生涯が描かれる。上巻に続き、いよいよ主な舞台を江戸から京都、そして九州へと、全国を股にかけての清河八郎の討幕の動きに拍車がかかる。八郎の信ずるモノがあまりに強いため、一見唯我独尊的な考えや行動が誤解を生むこともある。幕末の動乱期に、己を信じて一歩も二歩も先へ行動する強い意志が、多くの同志から賛同を得るも、一方で、意に反する者をも作ってしまう。まさに人の世の縮図を見ているようだった。 2023/08/01
takehiro
11
身近な人たちが次々と幕府に捕らえられても潜伏を続けていたのはどうかと思った。特にお蓮が哀れで仕方ない。清河八郎が有能なのはわかったけど、個人的にはあまり好きになれないなあ・・。2022/09/30
Hitoshi.F
9
読了。現実的には違うと思うが、思いのほか波乱もなく、ただ幕府の追手から逃れるが如く逃避行が延々と続く。青年期に文武を極めた逸材がいつのまにか目的と手段を履き違えたように「攘夷、攘夷」と騒ぎたて異人斬りや焼き打ちに走ろうとするところは異様にも感じた。清河八郎、この世に出現するのが少々早過ぎたか。御一新を果たしたこの国の真の逸材の面々との出会いに恵まれなかったことも八郎にとって残念だったであろう。ただ一人の男としては悔いのない人生だったのではなかろうか。2018/11/19
あかつや
7
上巻読んだ時はこれは清河八郎の印象がずいぶん変わってきそうだって思ったけど、最後まで読んだらだいたい元のと似たような所で落ち着いた。作者は一般に流布してる清河八郎像の誤解を解くために違う角度から光を当てようとしたみたいだけど、清河の心持ちがどうであれ表面に出ている行為が山師的だったり策士的だったりするなら、結局それは山師や策士ってことになるんじゃないかな。さすがに出世主義者とは思わなかったけど、主人公として好意的に描かれてもまだ好人物とはならないんだから、実際の人柄は推して知るべしってとこじゃなかろうか。2020/12/21
-
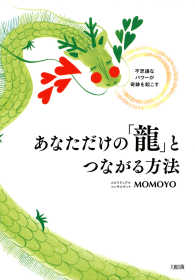
- 電子書籍
- 不思議なパワーが奇跡を起こす あなただ…