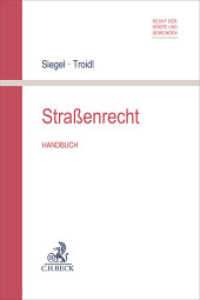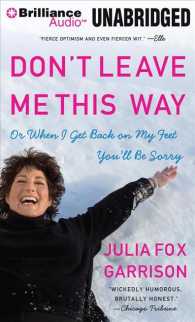出版社内容情報
「東京」に行けば何かを成せると思っていた。幕末から昭和にかけ涙を流しながら夢にすがる名もなき野心家達を暖かい筆致で描く。
内容説明
茗荷谷の一軒家で絵を描きあぐねる文枝。庭の物置には猫の親子が棲みついた。摩訶不思議な表題作はじめ、染井吉野を造った植木職人の悲話「染井の桜」、世にも稀なる効能を持つ黒焼を生み出さんとする若者の呻吟「黒焼道話」など、幕末から昭和にかけ、各々の生を燃焼させた名もなき人々の痕跡を掬う名篇9作。
著者等紹介
木内昇[キウチノボリ]
1967年、東京生まれ。出版社勤務を経てフリーランスとなり、インタビュー雑誌を主宰する。2004年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。2008年に発表した本書『茗荷谷の猫』で注目される。2009年、第2回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。2011年、『漂砂のうたう』で第144回直木賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
424
仲良しの読み友さんの間で人気の木内昇(のぼり・女性、お間違いなく)さん。正直第4話くらいまでは、読者に丸投げのようなラストに読みにくさを感じた。待てよ、これってビミョーに連作?と気づいたのが先か、『隠れる』の筆致にヤられたのが先か。幕末から、東京オリンピックの時代までの長いスパンで描かれた短編集。東京に住み、無名のまま消えていった人たちの、ささやかだけれどしっかりした日常が、わたしたちの心を静かに揺さぶるのだ。2018/08/02
mae.dat
273
ねこ、殆ど関係ない(´๑•_•๑)。特に歴史に名を残すでない 9名の主人公達に依る、江戸末期から昭和39年(1964年:東京オリンピック開催)迄の凡そ100年間。表題作を含む、9話短編(ショートショート長の物も)。東京(江戸)の下町中心の地名を添えて。どの話も、終着点を何処に置いているのか、どこに向かっているのかが分かり難くて、何を読まされているのか迷子になりましたよ。皆さん何かに取り憑かれた様にお仕事(?)に邁進するの。特に『黒焼道話(品川)』は、狂気を宿していたな( ໊๑˃̶͈⌔˂̶͈)。2025/08/24
yoshida
223
江戸末期から高度成長期までの人々の何気ない生活を描く連作短編集。最初の短編は江戸末期から始り徐々に時代が進む。後の短編になるほど、それまでに登場した人々のその後が分かり時代の変遷と儚さを感じる。特に好きな短編は「庄助さん」。映画を撮影する青年と、明かされる支配人の過去。戦争が青年を夢から切り離す。時代は変われど、続いてゆく人々の暮らし。そこにかすかに漂う先人達の暮らしの匂い。その儚さに胸を打たれる。そして、同時に今の私達の暮らしもいつかは儚い記憶となることを思い出す。思い出した瞬間、感慨が大きくなるのだ。2018/02/25
エドワード
178
江戸から昭和にかけて東京の片隅に生きた人々を描いた短編集。明治大正辺りの話は、妙薬を作ろうと懸命に努力した男、画家を志した女、高等遊民に憧れる男などの夢と現実を描いて、文豪の古典に似た味わいがある。それも異なる趣向で。昭和になると、戦争の影、戦後の悲惨さが加わる。最後の「てのひら」「スペインタイルの家」になると、もう戦後の豊かな日本が舞台だ。百年ほどの間に東京は何と大きく変貌をとげたことか。それが名もない庶民の目をとおしてうかがえるのだ。2011/10/05
酔拳
152
木内さんは、明治時代前後の時代を描くのがとてもうまいと思う。この小節は9編からなっていて、どの小説の主人公も大きなことをしようとしたり、懸命に生きていたりしている人を描いていますが、そのような人たちが、名すら残らず、時代に埋もれていってしまう様が儚いです。 9編の登場人物が微妙にからみあっているので、読んでいておもしろかったです。「染井の桜」で武士から植木屋になって、染井吉野を造った話はとても、興味深く読めました。2017/01/02