内容説明
「学びて時にこれを習う」。この有名な論語冒頭の一節は、“勉強して時々おさらいをする”と解釈する人が多い。だが、これは学校の勉強の話などではない。礼・楽の真の意味を知ると、全く違う解釈で思想の魔力が立ち上がってくる。論語を正しく読み解く時、単なる教訓・格言ではない活き活きとした知のドラマが見えてくる。
目次
変革者 孔子
文化を継承する者
目覚めた者
徳治という難問
詩と人性
文化の出発点としての詩
「淫」と恋歌
現実的な選択
節操と現実感覚
妖艶なる謁見〔ほか〕
著者等紹介
呉智英[クレトモフサ]
昭和21年、愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業。マンガ批評、知識人論など広い分野で執筆活動を行う。昭和63年から「論語」を音読する私塾を開講する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
52
論語についてはみなさんどのような読み方をされるのかはわかりませんが、この呉さんが書かれているような読み方をいつも心がけているつもりです。教条的な読み方ではなく比較的自由に読んでいます。そういう点でまさしく現代人があることについて考えるときにその関連するところなどを開いて読む読み方でいいのだと思います。宮崎市定先生の本もそうして読んでいます。2015/04/07
ビイーン
23
論語の解釈が深まる良書。特にこの一節が興味深い。「子日く、中行を得てこれに与せずんば、必ずや狂狷か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所なり」。孔子は地域共同体の規範を素直に信じているだけの温厚で円満な人を「徳の賊」と言い痛罵した。道徳を重んじた厳格な儒教のイメージは後世になってから作られたのか。やっぱり論語は面白いなあ。2019/10/19
モリータ
12
同様に経学儒教の解釈を避けて原儒教のあり方を求めようとした宮崎訳の直後に読んだからかすんなりと入る箇所が多かった。新約聖書を並行して読んでいたのでたまに出るキリスト教のたとえが嬉しい。しかし良い本というのは、次に読んでみたくなる本と共に読まなくてもよいと思える本を教えてくれる本のことかもしれない。2015/03/25
トッシー
6
世界最初の思想家と言われる孔子の言行録『論語』を読む前に是非読みたい本だと思う。孔子とその弟子たちとの人間関係が細かく描かれており、まるでそこにいたかのような錯覚をおぼえるくらいのエピソードが満載。また、彼らの人間性についても詳しく描写されていてとても面白い。中でも孔子と子路のやりとり(公冶長篇5-7)をユーモアと解し、厳格主義に反する孔子像が紹介されているところは特に印象的だった。硬いだけでなく柔らかい人間臭さを見せてくれる孔子さんを知って、『論語』をさらに興味深く読むことができるんじゃないだろうか。2011/07/23
カインズ
5
【形式的な論語の読み方を痛罵する】「論語読みの論語知らず」、この言葉を批判するために書かれた一冊と言っても良いかもしれない。様々な角度から論語を解釈し、時には厳しい批判を加える。また、孔子を単なる聖人ではなく、叛乱に参加しようとした変革者でもあるとも指摘し、新たな人間像を描きだす。そのような人間像で描かれた孔子と弟子達との会話が面白い。授業で学んだ論語が退屈だったという方は、読んでみてはいかかだろうか。2011/04/18
-

- 電子書籍
- 異世界で美味しいごはんを振る舞ったら、…
-

- 文具・雑貨・特選品
- Fonteミニガラスペン ブルー
-
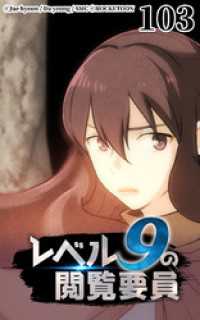
- 電子書籍
- レベル9の閲覧要員103【タテヨミ】 …
-

- 電子書籍
- レベル9の閲覧要員3【タテヨミ】 RO…
-
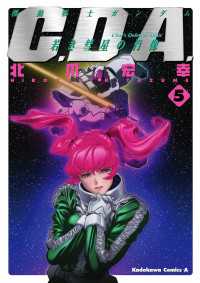
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダムC.D.A 若き彗星の…




