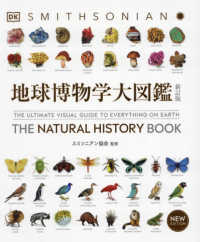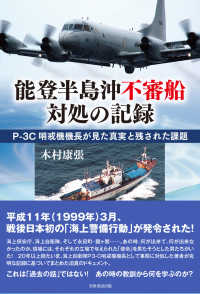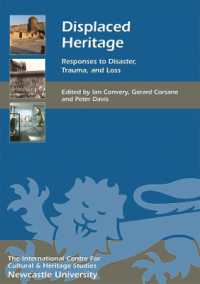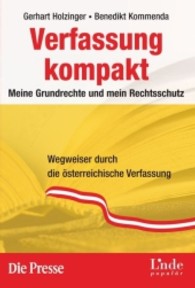内容説明
1980年代後半、「軟体動物みたいな、ビールの泡のような日本語がはびこる」現状や、人を言いくるめたり口喧嘩に勝つための屁理屈の達者さをよしとする風潮を、司馬はしきりに嫌っていたという。第2巻には大岡信との「中世歌謡の世界」、丸谷才一との「日本文化史の謎」等、6篇を収録。さまざまな角度から、日本語の本質に迫る。
目次
中世歌謡の世界(大岡信)
日本文化史の謎(丸谷才一)
空海・芭蕉・子規を語る(赤尾兜子)
日本語その起源の秘密を追う(大野晋)
日本の母語は各地の方言(徳川宗賢)
“人工日本語”の功罪(桑原武夫)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの蛩音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみちI”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大佛次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。平成5年、文化勲章受章。平成8(1996)年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クラムボン
19
最近丸谷才一の「日本文学史早わかり」を読んだばかりでして、この選集には執筆直後の司馬遼太郎との対談がある。丸谷から申し入れたそうで「日本文学史における宮廷文化と勅撰集の重要性」を話したかったことが伺える。「日本も日本人も鎌倉時代以降に生まれ、王朝文化は外国だと思っている」司馬さんとは拠り所が全く異なる。…その為か、丸谷の意気込みも一歩通行気味で、司馬さんに上手いことあしらわれた感じがする。今回は再読でもあり、6人との対談の内から他に詩歌を題材にした詩人の大岡信と俳人の赤尾兜子の回を読んでみました。2022/05/14
時代
13
司馬さんとの対談集。特に日本語についての括りで。言語の事は難しいです。ついていけない所もちらほらとあり苦戦しましたよ。もし司馬さんが今も生きていたら、現代日本語に憂いていただろうなぁ◯2020/02/02
jjm
12
国語学者等と司馬氏との日本語に係る対談集。徳川宗賢氏(田安徳川家)は方言の研究で著名で、日本の母語は各地の方言とまで言われている。祖母と職場の同僚で、タクシーで皇居近くを通ったときに皇居を指差して、いたずらっぽく、あそこは私の実家があった場所なんですよ、とお茶目な方だったと聞いたことを思い出した。『日本語練習帳』がベストセラーとなった大野晋氏は日本語の起源としてタミル語を推していた。あらゆる影響を排除した音節に着目したらしい(原日本語は二音節)。系統論的には批判が多く、やはり朝鮮語との類似性が多いらしい。2025/01/11
はかり
10
司馬が六人の研究者と日本語の生い立ちなどについて対談する。漢語から和歌、俳句、関西弁等々幅広い知識に目が回る。現代の文章などに関して、子規が特筆ものの功績を残したことがよく分かる。それにしても、日本語の奥深いことか。2018/07/27
でんすけ
7
言葉には、感情表現と論理性の側面がある。機能性や論理性ばかりでは、日本語の持つ情緒感覚が描写しきれなくなってしまう。標準語では、論理性はあるが感情に訴えるパンチに欠ける。この対談当時よりも日本語はずっと論理性たかく、機能性重視になっているだろうと思う。反面、洗練された情緒感は失われているかもしれない。ことばの重みはたぶん昔よりも軽くなった。進化した側面もあるけれど、失ったものもあるのではなかろうか。こういう本を読むと考えてしまいます。2016/07/31