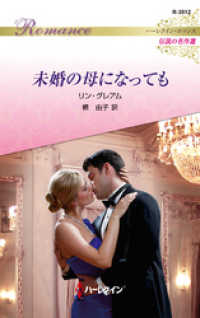内容説明
幕末の混迷期、なす術を知らない三百諸侯のなかで、自らの才質をたのみ、また世間の期待を集めた「賢侯」たち。かれら土佐の山内容堂、薩摩の島津久光、伊予宇和島の伊達宗城、肥前の鍋島閑叟は「藩主なるがゆえに歴史の風当りをもっともはげしく受け、それを受けることによって痛烈な喜劇を演じさせられた」。
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみち1”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大仏次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。平成5年、文化勲章受章。平成8(1996)年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Die-Go
110
再読。「酔って候」(土佐藩 山内容堂)「きつね馬」(薩摩藩 島津久光)「伊達の黒船」(伊予宇和島藩 伊達宗城)「肥前の妖怪」(肥前藩 鍋島閑臾)の幕末の藩主達を描いた四編の短編集。幕末においては西郷隆盛や坂本龍馬、新選組など家臣団の活躍が目立つため、どうしても裏方に回りがちな藩主達。ところがどっこい、この物語の主人公達は幕末の主役たりえるなかなかの個性派揃い。しかし、その個性が悲しくも喜劇的であったのが、読んでいて切なかった。★★★★☆2016/05/02
buchipanda3
105
自らを鯨海酔候と称した容堂候と言えば切れ者で豪胆ながら方針の豹変ぶりから怖い上司というイメージがあった。仕えた部下は散々肝を冷やしたと思う。そんな彼の若い頃からのエピソードが描かれ、酔狂な一面の根となる歴史主義と韓非子の思想からくる苦悩が見えてくる。なるほどこれは酔わずにおれようかという姿と思えた。他の3諸侯も独特な味を持ち、肥前の閑叟候の突っ走った感が凄い。ただ彼らは殿さまであり、激動の時代でもその範囲から外れなかった。最後の殿さまによる人生に酔った喜劇とも悲劇とも思える物語が何とも印象深く感じられた。2019/10/21
こきよ
65
四者四様、時代の変革期に足跡を残したお殿様達。やはり山内容堂の無頼ぶりが他の賢候を霞ませる。さては生まれた時代を間違ったか…2015/07/20
Book & Travel
64
TVの歴史番組で幕末・島津久光の率兵上京が歴史的に再評価されているという内容を見て、そういえば司馬さんは久光を辛辣に書いていたなあと思い出し手に取った。幕末、賢侯と呼ばれた四人を取り上げた短篇集。革命期にあってなまじ"賢侯"だった殿様達の人生は悲劇的でも喜劇的でもあって、小説には格好の題材のようだ。司馬さんの筆も冴え渡っているようで、短篇ながら読み応えがあった。中でも土佐には力が入るのか、山内容堂を描いた表題作が特に印象的。不遇のなか蒸気機関の製作に取り組んだ宇和島の提灯張り職人・嘉蔵の『伊達の黒船』も~2017/03/22
優希
63
面白かったです。自らの才能を認め、世間の期待を集めた「賢候」たちが描かれていました。歴史の風当たりを強く受けたからこその喜劇が語られているのかもしれません。2023/02/25