出版社内容情報
スターリンが、毛沢東が、マッカーサーが、トルーマンが、金日成が、そして凍土に消えた名もなき兵士たちが、血の肉声で語るあの戦争。
内容説明
「Die for a tie」(引き分けるために死ぬのだ)―中国参戦はないというマッカーサーの誤算が引き起こした消耗戦。この凄惨な戦争の始まりから終結までを、膨大な資料と生還した兵士たちのインタビューで詳述、その歴史的意義を新たな視点から照射する。ハルバースタムが10年の歳月をかけて取材執筆、最後の作品にして最高傑作。
目次
第7部 三十八度線の北へ(承前)
第8部 中国の参戦
第9部 中国軍との戦い方を知る―双子トンネル、原州、砥平里
第10部 マッカーサー対トルーマン
第11部 結末
エピローグ なされなくてはならなかった仕事
著者等紹介
ハルバースタム,デイヴィッド[ハルバースタム,デイヴィッド][Halberstam,David]
作家。アメリカが生んだ最も偉大なジャーナリスト。1934年生まれ。1955年にハーバード大学を卒業後、『ニューヨーク・タイムズ』入社、ベトナム特派員としての経験と広範な取材をもとに、ケネディ政権がベトナムの悲劇に突き進む様を描いた『ベスト&ブライテスト』(1972年)で大きな賞賛をあびる。以降、徹底したインタビューと、エピソードを積み重ねるニュージャーナリズムと呼ばれる手法で、アメリカのメディア産業の勃興を描いた『メディアの権力』(1979年)、日米自動車戦争を描いた『覇者の驕り』(1986年)など、骨太な現代史のテーマを次々とものにした。2007年4月23日、交通事故で死亡
山田耕介[ヤマダコウスケ]
1935年生まれ。元東京新聞・中日新聞記者。香港支局、マニラ支局長などを経て翻訳業
山田侑平[ヤマダユウヘイ]
1938年生まれ。元共同通信記者。ニューヨーク支局員、ブリュッセル支局長など歴任。人間総合科学大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
hayatama
チャゲシン
Miyako Hongo
Ryo
-
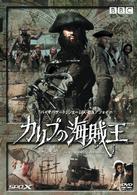
- DVD
- カリブの海賊王








