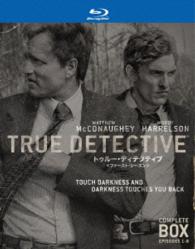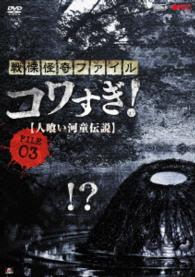内容説明
子供時代から寄席通いにはまり、作品の中で芸について触れたくだりが面白い夏目漱石。学業そっちのけで連日連夜、娘義太夫の追っかけをした志賀直哉。名だたる文豪たちは寄席や芸事と、意外な程縁が深い。圧倒的な数の文学作品を切り口に、寄席と文人の関わりを浮かび上がらせ芸の奥深さに迫る傑作コラム集。
目次
1 文人たちの寄席(谷崎潤一郎;折口信夫;芥川龍之介;高見順;久保田万太郎 ほか)
2 名作のなかの芸能(織田作之助『夫婦善哉』;伊藤整『誘惑』;五木寛之『銃声の夏』;尾崎士郎『人生劇場』;源氏鶏太『三等重役』 ほか)
著者等紹介
矢野誠一[ヤノセイイチ]
昭和10(1935)年、東京生れ。麻布学園、文化学院に学ぶ。演劇・演芸評論家、コラムニストとして活躍
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
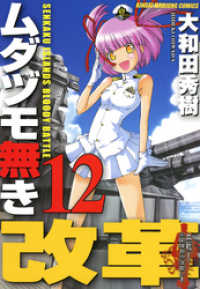
- 電子書籍
- ムダヅモ無き改革 12巻 近代麻雀コミ…