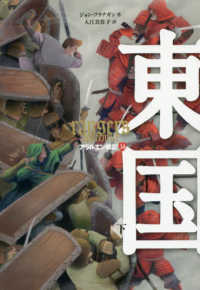出版社内容情報
「寿限無」「らくだ」などおなじみの古典落語について、あらすじ、味わい方などその面白さを新たに書下したファン必読の落語雑学事典
内容説明
落語は単なる落し噺しではありません。奥の深い芸なのです―おなじみ「時そば」「寿限無」から大ネタ「唐茄子屋」「文七元結」「妾馬」まで、選びぬいた三百三題を爼上にのせ、あらすじ、味わい方、噺家のエピソードなど落語に関するあらゆるエッセンスを、うんちくをかたむけてエッセイ風に書き下したファン待望の落語雑学集成。
目次
年の始めの…(御慶;万歳の遊び ほか)
春はあけぼの(厄払い;天王寺詣り;猫忠;長屋の花見;あたま山 ほか)
夏なれや(夢の酒;抜け雀;素人鰻;子別れ;牛ほめ ほか)
秋深し(蟇の油;てれすこ;お直し;締め込み ほか)
冬ざれの(藁人形;らくだ;うどん屋;時そば ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
16
1989刊。303席の演目(副題で上方と東京の異題)とあらすじに「うんちく」「能書き」「雑学」「味わい」「こぼれ話」「噺の成立」など、演目にあった著者ならではの思い出、所見、噺家の人(にん)のセンスをエッセイ風に。刊行が25年以上前のため、当時ですら既に故人の名人・上手の評は、いまや少ない音源でしか知る事の出来ない当時を感じられて個人的に良。上方東京偏らず噺、落語家も「生」で聴いている所見も良。同じ演目でも社会と時代が変わり、今演っているサゲと異なったり出典がの古典に多く採られているなど、興味深く読めた。2015/02/12
Nekono
3
かつて、よんどころない事情で入院してた頃、落語のCDを山ほど持ち込み、ひたすら聞いておりました。うんざりする病室の日々もヘッドホンから流れる落語で幾分か過ごしやすかった。とまぁ、そんな個人的事情から落語好きなのですが、色々聞いていくと落語が単なる滑稽話というだけではないってのが何となく感じ取れます。人情あり色事あり怪談ありのいわば総合話芸なのです。この本はそんな落語から303席を選び、あらすじ、うんちく、成立事情なんぞをつらつらと書き連ねたいわば、落語小辞典。お気にの落語を聞いて読むとまた興が増します。2011/08/30