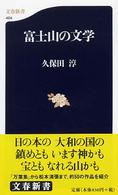出版社内容情報
"死"と向い合うことは、"生"を考えること。長年、納棺の仕事に取り組んだ筆者が育んできた詩心と哲学を澄明な文で綴る"生命の本"
内容説明
掌に受ければ瞬く間に水になってしまうみぞれ。日本海の鉛色の空から、そのみぞれが降るなか、著者は死者を棺に納める仕事を続けてきた。一見、顔をそむけたくなる風景に対峙しながら、著者は宮沢賢治や親鸞に導かれるかのように「光」を見出す。「生」と「死」を考えるために読み継がれてほしい一冊。
目次
納棺夫日記(みぞれの季節;人の死いろいろ;ひかりといのち)
『納棺夫日記』を著して