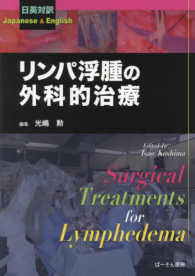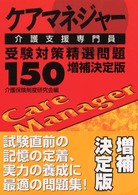内容説明
2002年秋、80万人の中学生が学校を捨てた。経済の大停滞が続くなか彼らはネットビジネスを開始、情報戦略を駆使して日本の政界、経済界に衝撃を与える一大勢力に成長していく。その後、全世界の注目する中で、彼らのエクソダス(脱出)が始まった―。壮大な規模で現代日本の絶望と希望を描く傑作長編。
著者等紹介
村上龍[ムラカミリュウ]
1952年、長崎県佐世保市生れ。武蔵野美術大学中退。大学在学中の76年に『限りなく透明に近いブルー』で群像新人文学賞、芥川賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
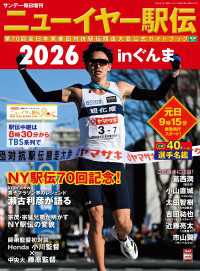
- 電子書籍
- サンデー毎日増刊 ニューイヤー駅伝20…