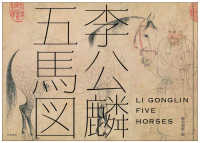出版社内容情報
夫も財産も戦火に奪われ頼るべきものもなく寒々と疎開先で暮す母子二人、その母も死に追いこまれていく…精緻で清洌な文体にのせて描いた第54芥川賞受賞作品
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
231
作者自身の少年時の体験を後年に回想したものに見えるが、実際はフィクションであり、時代状況は共有するものの、それ以外は仮構されたものである。そうしてみると、高井有一の小説としてのリアリティは、極めて高いということになる。選考委員の川端康成が「抑える作風」と評しているが、その抑制された筆致こそが、この小説の特質だろう。全く唐突に死んでいった母は戦後の状況の中で、しかも東北の地での展望は描きようもなかったのだろう。そして、とうとうそれを了解できない「私」の孤独は深い。その断絶が埋められることは永久にないのだ。2015/11/25
遥かなる想い
189
第54回(1965年)芥川賞。 戦後の残された人々の風景を、抑えた 筆致で 描いた物語である。 疎開先の東北での母との日々が 怜悧に語られる。地味で 薄暗い物語だが、 息子の母への視点が、哀しく印象に残る、 そんな話だった。2017/08/17
燃えつきた棒
34
《ふるさとの訛りなつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく》(石川啄木『一握の砂』より。)/ 母は秋田県由利郡、現在の由利本荘市の生まれで、僕も子供の頃、よく母に連れられて、秋田に帰省した。 実家に帰ると母は、たちまち秋田県人へと豹変し、兄弟姉妹や友人たちと秋田弁で饒舌に喋っていた。 その言葉は、生まれは秋田市だが千葉育ちの僕には意味が分からないこともあったが、その懐かしい響きは今も耳に残っている。 はたして、秋田ゆかりの作家が秋田を描いたというこの小説に、その響きを聴くことができるだろうか?/2024/05/31
マサキ
9
重い。表題作は母のみならず、私をも徹底的に客観視し、絶望を語らない。それはその時の正直で率直な感情だろうが、時代を経た視点から書く以上、失ってしまったもの、分かったもの、あきらめたもの、など本当は「そうではなかった」ところがあるはずだ。その「そうではなかった」ところが、作品の通底音として表には現れずに、存在感を放っている。重い。2020/07/10
かさねパパ
5
約40年前の本です。身近な死が主題となってますが、死の情景を淡々と描いてます。身近の事でありながら、感情的ではなく他人事のように、周囲の情景や人間を絡ませ書いてますが、逆にそれがこの小説の魅力でもあり、怖さ、難しさなのかなと思います。文章は簡潔で読み易いですが、修飾が古典的な印象、福永さんや辻さんに近いものを感じます。今は直接的な表現が好まれように思いますが、それに慣れるとやや読みにくいかもしれません。ただ、ここで描かれてる青春は、今では死語となってしまった、そんな鬱屈した、でもエネルギッシュな青春です。2016/01/03