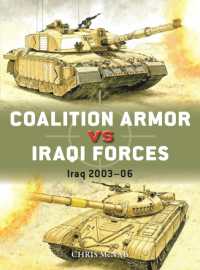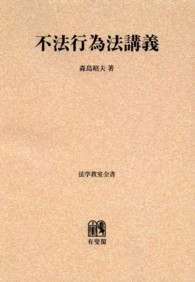出版社内容情報
肉親の死、友の死、戦争の死、今までめぐりあってきたさまざまな死にひそむ人の営みの奇妙さをあざやかに描き出した円熟の十短篇
内容説明
生きるということは、死と出逢い続けることでもある。肉親の死、友人の死、戦争による死、病いによる死、あきらめのよい死、恨みを残す死―。生にいろんなかたちがあるように死も多様だ。いままでめぐりあってきたさまざまな死に鋭い観察の目を向け、そこに潜む不条理をあざやかに捉えた豊かで精妙な短篇集。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mondo
42
「死」に関する短編が10篇納められている。いずれも、私小説で主人公である「私」は吉村昭自身である。最初の「金魚」では、吉村昭の幼少期から18歳で徴兵検査に合格するまでを描く。すでに本人は肺病を患い、兄を中国戦線で亡くしている。悲惨な戦禍の中で、唯一鮮やかな朱色で目を楽しませていたのが「金魚」だった。極限状態の中での人々の生と死が淡々とした表現で語られている。また最後の「屋形船」は昭和60年代。花火を観に深川から千住新橋までの移ろう景色の中で、戦中、戦後の出来事が走馬灯の如く語られていく。好きな短編の一つ。2023/09/23
ぼちぼちいこか
12
金魚、煤煙、初富士、早春、秋の声、標本、油蝉、緑雨、白い壁、屋形船 の短編10話。いずれの話も吉村氏の実体験を書いている。金魚と戦争というのは結びつきがなかった。煤煙はヤミ米の買い付け。初富士はある年の正月。早春は従兄への見舞い。秋の声は禁酒していた頃の思い出。標本は切除した自分の肋骨との対面。油蝉は従姉の葬儀。緑雨はある女流作家の葬儀。白い壁は病院の思い出。屋形船は少年時代の思い出が書かれている。一番心に残ったのは、やはり標本だ。 2020/05/28
黒豆
8
死を意識せざるおえない、長い入院による闘病生活や葬儀での交流風景など、作者の経験から生み出されたと思われる10編の短編物語、自身も同様な経験が多々あり共感しながら読みおえた。ストーリーとは別に 白い壁 の出だしで驟雨という言葉で始まり、どんな意味?と思い調べる→にわか雨、夕立、2017/10/27
fubuki
5
「あとがき」を読むと、短編集を編むにあたって「死」に関するものばかりが集まったとか。年齢を重ねると、こういう情景が多くなるものだが、それにプラスして「戦争」という大きな「死」も存在した。淡々とした記録のような文章で、小説として読むと面白みに欠ける。ただ、死を前にしていると、生きていたいという思いが強くなるのかもしれない。ある意味、生きて行く指南書になっているかもしれない。生きて行くことは、誰かを、何かを犠牲にすることかもしれない。2018/08/09
きりだんご⭐️新潮部
4
●知人より2024/11/02
-

- 電子書籍
- 中学受験 小6になってグンと伸びる子、…