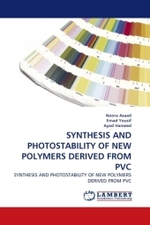内容説明
室町幕府の全盛期を築いた将軍、足利義満。冷徹な計略で天皇の地位をも狙う野望を抱きつつ、絢爛たる北山文化を繁栄させ、世阿弥と耽美な交わりを結ぶ。しかし、栄華の裏で、義満は、乳人への秘めた恋心に苛まれていた。その孤高な魂に去来する思いとは。新たな視点で、人間・足利義満を描いた渾身の歴史小説。
著者等紹介
平岩弓枝[ヒライワユミエ]
昭和7(1932)年、代々木八幡神社の一人娘として生れる。30年日本女子大国文科卒業後、小説家を志し戸川幸夫に師事。ついで長谷川伸主宰の新鷹会へ入会。34年7月「鏨師」で第41回直木賞を受賞。平成3年「花影の花」で第25回吉川英治文学賞受賞。平成10年、第46回菊池寛賞を受賞。テレビドラマ、芝居の脚本も数多い
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
真理そら
68
『銀閣の人(門井慶喜)』が面白かったので金閣の人(義満)の話も読んでみた。王者の孤独というか孤独に耐えられる人しかトップでいられないというのはいつの時代も同じかもしれないと思ったり…一種のマザコン的な初恋があったから孤独にも耐えることが出来たのかもしれない。義満の皇位簒奪的な明貿易における日本国王印も相手が天皇ではなく義満だったから日本は明の属国にならなくて済んだともいえるかもしれない。平安時代から現代まで続く権威としての天皇と権力としてのトップが分かれているのは日本にとってはいいシステムだと思う。2021/01/08
エドワード
14
最近読んだ三島由紀夫の「金閣寺」に触発され、足利義満伝に挑戦。幼き日は親子兄弟が争う下剋上の世。その渦中で若くして将軍となり、皇家、武家、公家、僧侶を巧みに操る手際は見事だ。法体となった義満の姿は、藤原道長か後白河法皇を彷彿とさせる。中国で元から明へ王朝が交代するのを見た義満の野望は日本国王の座へ向かう。燦然と輝く金閣こと鹿苑寺舎利殿は、武家、公家、佛教の三界の支配者の姿を具象化したものであった。義満の良き理解者、二条良基が義満に遣わした美形の僧、三宝院満済の密命とは何か。義満の死の真相やいかに。2013/03/07
紅花
13
義満の真の恋人乳母玉子、彼の孤独な心をうめる黒衣の宰相満済、世阿弥。この三人が義満という人を、そして成熟の時を迎えて、ある意味分かりにくかった足利幕府(南北朝の人間関係、大陸との貿易、九州のいざこざなど・・)というものを、整理してくれた。初、平岩弓枝さん、予想以上に面白く読めました。2014/09/19
日の光と暁の藍
13
三代将軍足利義満には、管領の細川頼之という実に優れた側近がいたことを知る。本書は、義満が皇位簒奪を企てたとして描かれている。今日、学説としては批判されているが、義満が皇位簒奪を企てた理由まで平岩氏は本書で描いている。義満以外の主な登場人物は、細川頼之、頼之の妻玉子、京極佐々木導誉、観阿弥、世阿弥、二条良基、斯波義将、一条経嗣、三宝院満済、後円融天皇、崇賢門院など。細川頼之と義満の関係が凄くいい。斯波義将の反頼之の陰謀、明との交易を巡る義満の実利主義、三宝院満済の焦り、義満の孤独など、実に興味深く読めた。2014/07/16
のこ
11
足利三代将軍・足利義満の誕生から死まで。義満というとあの下がり眉の僧姿が思い浮かびますが、この小説では雄々しく自信と野心にあふれ、何者をも恐れない一人の男でした。それでも心では独りであることを理解していて、そのギャップが切ない。■義済が、金色の舎利殿を見て号泣→義満に抱かれるまでの流れがすごい。鳥肌ものでした2013/11/07
-
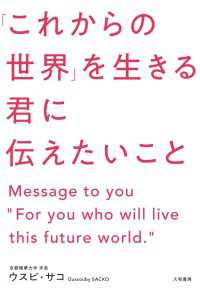
- 電子書籍
- 「これからの世界」を生きる君に伝えたい…