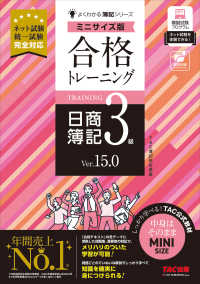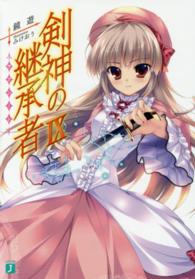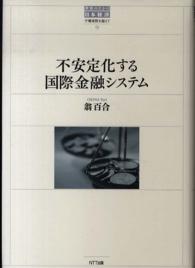内容説明
文久二(1862)年四月二十三日、伏見の船宿・寺田屋の二階。長州と手を組んでクーデターを謀る薩摩誠忠組の動きは、長州嫌いの久光の怒りを買った。蹶起中止を説得する使者との間に朋友相討つ惨劇が起る。武士にとって藩命と理想、君命と朝命はいずれが重いか、この時点でこれは答えの出ない命題だった。
著者等紹介
海音寺潮五郎[カイオンジチョウゴロウ]
明治34(1901)年、鹿児島県に生れる。国学院大学を卒業後、指宿や京都で中学校教師を務めるかたわら創作にはげむ。「サンデー毎日」大衆文芸賞受賞を機に、執筆生活に入る。昭和11年、『天正女合戦』で第3回直木賞を受賞し、文名を不動のものとした。昭和52年12月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TheWho
14
文久2年4月23日(1862年5月21日)に薩摩藩尊皇派が薩摩藩主の父で事実上の指導者・島津久光によって鎮撫された事件で、所謂「寺田屋騒動」と云われた幕末の悲劇に至った経緯を歴史小説家の大家が詳細に語った一冊。従来の著者の作品と違い塩野七生風の語り口であり、よりリアルに寺田屋騒動に至る幕末の世相を語っている。多分読み手は、小説と歴史書の狭間で困惑しているかも知れない。これも今の塩野七生作品と共通している所であろう。幕末史の名作と思われる一冊です。2016/11/27
さっと
8
著者が『幕末動乱の男たち』の中で「薩藩維新史上の大汚点」と言っていたのが、幕末、薩摩藩士が相討つ始末となった寺田屋騒動。史伝とはいっても、ですます調で書かれていて、かみくだかれた感があって読みやすい。公武合体と倒幕の対立は多くの藩内で反目があって歴史を騒がせてますが、明治維新の主役・薩摩藩も例外ではなかった。2018/05/14
みやざき しんいち(死ぬまでにあと1,000冊は読みたいんだ)
8
[29/1000] 鹿児島の人は、先祖を愛し歴史を愛し鹿児島を愛している。うらやましいかぎりだ。そんな鹿児島の大口が産んだ作家、海音寺潮五郎は、文章の端々に丁寧に先祖をなぞっていこうという気持ちが見えて、とてもすがすがしく読むことができた。2018/04/23
TK39
5
薩摩人の尊王攘夷の急先鋒の一派を島津久光が上意討ちした寺田屋騒動。小説ではなく事実を追っている。将軍の世紀下巻を読みつつ、なぜ寺田屋事件が起きたのか、薩摩側の事情を知りたくなった。有馬新七は猪武士だと勝手に思っていたが、学もあり武芸もできる人だったとのこと。維新の先駆けだったのは間違いないが彼が生きていたら、維新はどうなっていたか。2023/11/12
あかつや
3
龍馬じゃない方の寺田屋事件。島津久光による薩摩藩志士粛清事件をその源まで遡って丁寧に読み解いていく。読者に向かって語りかけるスタイルで、小説というより講義録を読んでいるかのよう。これ朗読するだけで大学の授業をでっち上げられそうだ。筆者によるとこの事件は「一見したところでは、単なる薩摩藩内の内紛」であるが、実は「幕末維新史を複雑困難にした薩長反目の最初の契機」であり「なかなか重要な事件」であるとのこと。しかしやっぱりお侍ってのは大変だよ。同朋であっても話が合わなきゃ刀抜いて刺しつ刺されつしかないんだもんな。2022/05/08
-

- 電子書籍
- ざつ旅-That's Journey-…