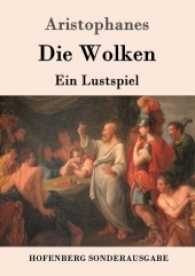内容説明
底なしの執拗さでまとわりつき、被害者の生活を破壊するストーカー。「古典的ストーカーと現代的ストーカーの相違点」「ボーダーライン人格障害とストーカーの関係」「幼少期のトラウマがストーカーを生むのか」など、現役の精神科医がその病理を余すところなく分析する。現代社会論としても秀逸な一冊。
目次
第1章 ストーカーたちの心の闇―コントロールできない異常愛とは
第2章 古典的ストーカーと現代的ストーカー―標的になった有名人たち
第3章 「普通の人」がストーカーに変わるとき―想像を絶する「執拗さ」の理由
第4章 なぜ偏り歪んだ心になるのか―一見、見分けがつかない人格障害の恐怖
第5章 ストーカーをいかに見破るか―次にあなたが狙われないために
第6章 「ストーカー」現象は、このあとどうなる?―屈折愛を増長する時代の病理
著者等紹介
春日武彦[カスガタケヒコ]
昭和26(1951)年、京都府生まれ。日本医科大学卒業。精神科医として都立松沢病院に勤務するかたわら、精力的に執筆活動を展開
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
17
精神科医の春日武彦さんの著書。親本は平成9年だったらしいです。私見ですが、精神用語みたいなのは、 私の小さい頃はほぼ和語ばかりでしたが、近年はかなりマニアックな概念とかも、横文字で一般化して子供でも使う様になりましたね、その最たるモノがトラウマだと思いますが、このストーカーもそうですし、アダルト・チルドレン、サイコパスなんかも。さて人格障害と精神病はどう違うかとか、基本的な事を丁寧に解説してくれます。大事なのは、精神医学や心理学は基本的に後知恵であり、理解と説明の為の学問であり、予測予言の学問では無い。2024/11/23
魔魔男爵
5
ストーカーブームの時の本だが、便乗本ではない。ストーカーという名称を広める切っ掛けになったリンデン・グロスの『ストーカー/ゆがんだ愛のかたち』の解説者が春日先生だったので、春日先生には、ストーカー評論家第一号を名乗る資格があるw。具体的なストーカー対策は地方農村に移住汁!ぐらいしかなく、ストーカーに困ってる人にはあまり参考にならないかも?精神分析用語を茶化したギャグをやってる面白い読み物である。ストーカーは基地外さんなら治療も可能だが、人格障害者なので、逃げるしかないざんす。ストーカーややばい人に遭遇する2018/01/06
erie
4
ストーカーについて、統合失調症によるものと人格障害によるものとに分類し解説している。新しい言葉(特に、多数派ではない声質を持つ人を指す言葉)がパッと広まる過程についての考察、ものごとを安直に単純化して娯楽に落とし込むメディアへの批判なども鋭い。これまでいくつか(真っ当な)精神科医の本を読んできたが、彼らは総じてユーモアのセンスがあるなあという印象。本自体が古いので、家庭のあり方の前提などが古いのが難点か。愛読書とその人の精神の傾向についての記述があり、遊び半分の記述と解釈したがちょっとドキッとした。2018/10/21
晴間あお
4
ストーカーの精神構造を冷静に分析している印象。オタクとしてはヤンデレを思い出さずにはいられない。ストーカーの精神構造は他人事ではないようで、「安直なデジタル的発想、予断や憶断による決めつけ、被害者意識を通じての自己正当化といったものは、常にわれわれを誘惑しつづける」と著者。「ありのままで生きよう」というのも発想が似ている気がする。「ありのまま」なんでもわかりあえる関係か、わずらわしい他者として排除するか、というデジタル。折り合いをつけるというグラデーションの無さ。そういう点がストーカーと似ている気がした。2018/04/08
Ted
4
'01年12月刊(底本'97年3月)◎残念ながら今では報道に接しない日がないほど人口に膾炙してしまったストーカーの性格的諸元と病理を精神科医が鋭く分析。戦後、アメリカだけをモデルにひた走って来たのだから当然の結果だろうが、日本で問題になり始めたのはアメリカに遅れること数年の'96年秋頃からだという。日米以外でも同様の現象は起きているのだろうか。ストーカーのタチの悪さは、一見しただけではその異常さを見抜けず、寧ろ善人を装ってすらいるので普通の交際が暫く続くが、ある日ふとしたきっかけで突然本性を現す点である。2014/10/16