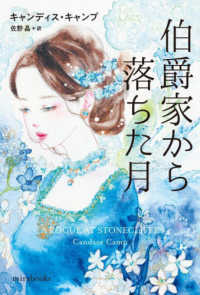出版社内容情報
さまざまな角度から歴史における日本文化の特殊性を分析・考察する司馬史観の集大成。竜馬、松陰等を語った「人間の魅力」も収録
内容説明
「葦原の瑞穂の国は神ながら言挙げせぬ国」(万葉集)―神ながらということばは“神の本性のままに”という意味である。言挙げとは、いうまでもなく論ずること。神々は論じない。―神道や朱子学はわが国の精神史にいかなる影響を与えたか。日本人の本質を長年にわたって考察してきた著者の深く独自な史観にもとづく歴史評論集。
目次
神道
会津
大名と土地
鉄
室町の世
連歌
宋学
看羊録
藤原惺窩
不定形の江戸学問
人間の魅力
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゴンゾウ@新潮部
126
神道、鉄、宋学を数回に分け多くを割いて書いている。土着の自然信仰だった神道と大陸から伝来した仏教を融合させた日本人の歩み。農業の発展に絶大な威力を発揮した鉄と日本人の関わりをあらゆる角度から考察している。何と言っても面白かったのは巻末の「日本人の魅力」。司馬さんが描いた幕末の志士たちの魅力が満載である。 2017/10/07
Die-Go
85
再読。日本と言う国の「かたち」を、司馬遼太郎の筆によって読み解く。司馬遼太郎と言うと、戦国及び幕末・明治の小説のイメージが強いが、その知識は古代にも及んでいる。本巻では神道、鉄などを古代史から語っている。★★★★☆2016/04/26
カピバラKS
80
●平成6・7年の文藝春秋巻頭随筆。●幕末の志士吉田松陰は、松下村塾において、生徒の長所を的確に評価し、褒める教育を施すことで、幾多の優秀な人物を育成した。●ところが、例外があった。伊藤博文である。松陰は伊藤を「才おとり、学おさなき」と酷評し、ただ「周旋の才あり」としたに過ぎなかった。お調子者の仲介上手といったところか。●松陰は優れた教育者であった。それでも、伊藤の大才は見抜けなかった。人の評価の難しさに慨嘆するほかはない。2024/09/25
k5
62
「日本に最初にイデオロギーが入ったのは、十四世紀の鎌倉時代の末期ごろである。宋学とよばれた。鰻屋の蒲焼の香りが路上までただよう程度の入り方ながら、影響は激甚だった。」司馬遼太郎のエスプリについて思いをはせたくて、このシリーズを読んでいるので、こういう表現に出会うと嬉しくなる。しかもこの宋学イデオロギーというのは、華と夷を分つという意味で、その民族差別的なところがどうしても司馬さんの嗜好に合わないのであろうところが信頼に値します。あと一冊。2024/04/28
優希
59
神道や朱子学は日本の精神史にどのような影響を与えたかという考察が興味深かったです、日本人の本質を長年考察した司馬さんならではの疑問なのかもしれません。巻末の雑文も面白かったです。2023/03/29
-

- 電子書籍
- ういちの島 5巻(完) バンチコミックス