出版社内容情報
本来なら学校に行っているはずのわが子が毎日家にいる。その姿を見る親や家族は、これほどつらく悲しく、無念なことはないと言う。学校も、そこにいるはずの子どもがいない、寂しく残念なことだと嘆く。子どもの数は減りながら、不登校は全国あまねく、男女の別なく、親の職業にも関係なく、発生比率を高めて増え続けている。現在、地域で差はあるが、小学生は25人に1人、中学生は10人に1人が不登校のようだ。
また、教室でなく別室に登校する子どもたち、フリースクール等に通う子どもたちを加えれば、その数はさらに増す。高校生は休学や退学、進路変更のことがあるので正確な数の把握は困難であるが、不登校の子どもたちの多くが進む通信制単位制高校の卒業率が、ごく少数の高校を除いて、3割程度と言われているので、学校不参加の子どもたちは膨大な数にのぼる。加えて社会的引き籠もりの人たちの数を入れると、この問題はこの上なく深刻である。
学校は、子どもが人に成るために必修の学びと生活の場であり、就学し、願う学歴を取得するところである。わが国の学校教育は一律の就学を制度としている。そのおかげで私たち日本人は、等しく教育を受ける機会を得て、生きるために必要な知識や技能を習得する。また、人と時間を共有して、より好ましい人間性を身につけ、その人らしい意味ある人生を全うする契機を得る。学校は価値ある人生を創造する貴重な学びの場である。
不登校問題は一日も早い解決が必要である。再登校や再就学が実現したときの子どもたちの安堵とうれしい表情は、実に爽やかで美しい。周囲の喜びも一入である。幸せが訪れる。私たち日本人は、この問題の発生を抑止し、子どもたちの再登校と再就学を具現するために、この問題を他人事にすることなく、愛と知恵、感性、行動力を結集して問題解決を図り、幸福感をともにする必要がある。
かなり長い年月、いくつかの心理職の資格を得て、市井の片隅で、新生児から大学生までの子どもたち、親や家族、そして教師などの教育相談(カウンセリング)に携わってきた。子どもたちが抱えるあらゆる問題に関わってきたが、昨今、特に多いのは不登校問題の相談依頼である。
不登校問題に関する教育相談のねらいは再登校と再就学の実現である。それは、この問題の本質と個々の事例の問題の所在を正しく理解し、手だてを工夫し、手順に従い、知恵と感性をはたらかせれば、再登校と再就学はほぼ実現する。この書では、心理療法を学び、また数多くの臨床事例から習得した不登校問題の解決のための考え方や具体的な方策を明らかにする。
また、これまでの教育相談で、子どもたち、親や家族、教師等からたくさんのことを学んだ。それらを基に、不登校を生まない子育てや学校教育のあり方、社会一般の人たちへの関与の願いなどの提言を行う。行政当局への要望等も付した。
【目次】
まえがき
Ⅰ 人としての自然な心
1 使命
2 人としての自然な心
3 心に留めおくこと
Ⅱ 子どもたちの発言、根源、解決のしかた
1 子どもたちの発言、その変容と特色
1 発言の変容と特色
2 子どもたちが語る不登校になった事情や理由
2 不登校問題の根源
1 不登校の定義と要因
2 問題の根源
3 根源に付随する三つの特性
4 性格による不登校の発生
3 解決のしかた、その基本
4 不登校の歴史の概観
Ⅲ 定義、発生機序、要因、タイプ、対策
1 定義、課題
2 発生機序、構造、タイプ
1 発生の機序
2 発生脆弱性の形成と不登校の発生
3 発生の構造(メカニズム)
4 不登校の型(タイプ)と随伴症状
5 昨今の特性
3 きっかけ、その対処
1 きっかけの把握と解決
2 学校でのきっかけ
3 きっかけの解決
(1)正確な把握
(2)軽重の判断
(3)解決のために大切なこと、すくむ反応の有無
(4)家庭でのきっかけ
4 長期化、二次的問題
1長期化の目安と課題
2 長期化の要因
(1)何もしないこと
(2)長欠感情への捉われ
(3)偽解決と悪循環
3 二次的な問題
(1)ゲーム中毒、インターネット依存
(2)引き篭もり
4 親の責任、心ある第三者の探索
5 誘因=不登校の不登校、その対処
1 要因
2 心理的外傷体験
3 いじめの問題
(1)いじめの深刻さ
(2)SNSやラインでの誹謗中傷
(3)発達障害の子どもたちへのいじめ
(4)いじめをする子どもたちの特性
Ⅳ 問題の解き方、道筋、手だて
1 再登校への道筋
1 原則
2 辿る道筋
3 思慮開始期から適応期までの実践事項
2 不登校にならない子どもたち
1 子育ての弁え
2肯定的自己像の内容と形成
3 問題解決のしかた
1 親密な時間の累積
2 親密な関係形成の手だて
Ⅴ 煩悶、人との出会い、内的成長、新しい生き方の創造、総括
1 内的成長
2 悔悟、煩悶、思考、試行錯誤、自立
1 子どもの悩み、思考、試行錯誤、自立
2 再登校の子どもたちの告白
(1)小学4年、女子、自己工夫、自力解決
(2)中学2年、男子、煩悶、自力更生
(3)小学6年、女子、涙と心の自己考察、自律的解決
(4)中学3年、男子、内的成長、自立
(5)中学1年、女子、自己変革、尻込みからの脱却
(6)14歳から5年、引き篭もりの男子無業者、対人恐怖の克服、外へ
3 親や家族の変容、好ましい成果
1 不登
内容説明
直近の数字で言えば、小学生は約50人に1人、中学生は約15人に1人が不登校である。未曽有の事態と言えるだろう。著者は40年以上にわたって、不登校の子どもに関わってきた。本書はその解決の糸口を、詳細に解説した本邦初の労作である。悩める親、教師、役人、心理職に、ぜひとも読んでもらいたい。
目次
1 不登校問題の根源
2 不登校発生のメカニズム
3 解決への道筋と手だて
4 成長、変容、そして克服
5 教師と学校の対処
6 カウンセリング(教育相談)の実際
7 医療に関する事柄
8 不登校を生まない家庭、学校、社会
9 予後と提言
著者等紹介
海野和夫[ウンノカズオ]
特定非営利活動法人学童保育すばる森合理事長。1938年福島県生まれ。福島大学卒。福島県公立学校教員、福島県教育センター教育相談部、二本松市教育委員会などを経て、校長職4校(小学校1校、中学校3校)。財団法人国民保健会などで教育相談に従事。元臨床心理士・学校心理士・家族心理士(いずれも資格更新せず)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
totuboy
Go Extreme
Avocado Senpai
ちもころ
shun11suke
-
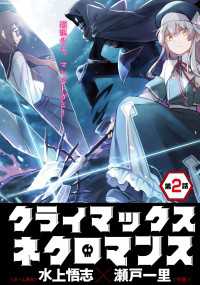
- 電子書籍
- クライマックスネクロマンス 連載版 第…








