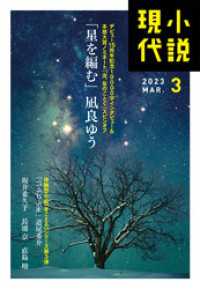出版社内容情報
「体験格差」という言葉の響きがもつ薄気味悪さを手がかりに、
大人たちを「体験の詰め込み教育」に駆り立てる「呪い」の正体に迫る!
大学入試の変化や非認知能力ブームで、子どもの体験までもが課金ゲーム化している。親たちは体験の詰め込み教育に駆り立てられ、子どもたちは格差意識を刷り込まれる。まるで「体験消費社会」だ。
体験をたくさんしたほうがいいと煽られた結果、お金のある家庭の子どもたちはたくさんの習い事をさせられ、かたやお金のない家庭の子どもたちは遊ぶ相手すらいない状態で地域に残される……。そんな、小学生たちの放課後の分断が、あるNPOの調査結果から浮かび上がってきた。
著者は、100年以上の伝統があるキャンプから、プレーパーク、無料塾、駄菓子屋さんまで、体験を通した子どもたちの学びの現場を訪ねる。現場からは、「体験格差」という概念そのものに対する疑念や困惑や批判の声が相次いだ。
本書は最後に、体験消費社会に対して3つの警告を発する。著者が発する3つの警告について、体験格差解消を掲げて活動する複数の団体からの回答もそのまま収録されている。
内容説明
習い事ゼロじゃダメですか?教育格差から体験格差へ!?課金ゲームに煽られる親たちと格差を刷り込まれる子どもたち。友達と遊びたいだけなのに…本当に必要な体験は?
目次
第一章 学力から非認知能力へ、お勉強から体験へ(課金ゲーム化する子どもの学び;非認知能力のインフレが止まらない;ハイパー・メリトクラシー化する日本社会 ほか)
第二章 子どもにとって本当に必要な体験とは何か?(一〇〇年以上の歴史がある組織キャンプ;子どもたちを「アリ化」する体験;できるひとは他人のために余裕を使おう ほか)
第三章 裏山の秘密基地が消えた社会で(体格格差はあっても体験格差なんてない;体験に関してお金の問題は二次的な問題;必要なのは“理想の学校”より駄菓子屋さん ほか)
著者等紹介
おおたとしまさ[オオタトシマサ]
教育ジャーナリスト。1973年、東京都生まれ。麻布高校出身、東京外国語大学中退、上智大学英語学科卒。リクルートから独立後、数々の教育誌の編集に携わり、現在は独自の取材活動をもとに幅広い媒体に寄稿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
本詠み人
よっち
りょうみや
Eric
崩紫サロメ