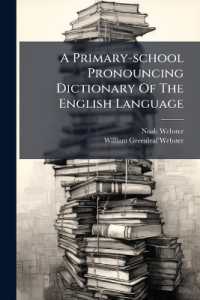出版社内容情報
人は誰しも生きている間に言葉を遺すものだ。ましてやひとかどの人物ならば、その言葉はしばしば含蓄に富んでいる。
送る側も、生前の偉人の言葉には激しく反応するから、追悼文はしばしば言葉の宝庫となる。
そんな言葉を集めてみたいという動機のもとに編んだのが本書である。
第一章では、松下幸之助、丸山眞男、石原裕次郎、千代の富士、やなせたかし、吉本隆明、小山内美江子、大平正芳などの、知られざる側面が、彼らを「師」と仰いでいた人物によって語られる。側近、もしくは身近な者だけに晒した「生の言葉」「生の姿」の迫力が凄い。
第二章では、水木しげるの晩年と壮年の日々を、奥様と娘二人が思い起こす。美術館であまりに解説がうまいために学芸員に間違われたエピソード、手塚治虫への想い、水木作品が古びない理由などを語る。
第三章で登場するのは美空ひばりである。最期の「不死鳥コンサート」に至るまでと、それを成し遂げたあとの凄まじいエピソードが明かされる。
第四章で語られるのは、稀代の作家にして政治家であった石原慎太郎であるが、息子の目を通した素顔はわれわれが知る姿とはかけ離れている。「オレは思いっきり女々しく死んでいくんだ」の真意とは?
第五章で阿川弘之を論じるのは、倉本聰氏である。氏にとっては、作品・人間・生き方・思想、そのすべてが好きで、まさに「師」以外の何物でもなかった。
第六章で立花隆を語るのは佐藤優氏である。二人は共著をものしているのだが、最初から立花とは波長が合わなかったと追想する。最後に佐藤氏を立花に近づけたものは何だったのか。
そして、本書では、保阪正康氏による半藤一利、澤地久枝氏による中村哲への追悼がつづく。
追悼文は、送り送られる人たちの、人生の縮図なのである。
内容説明
リーダーの言葉は研ぎ澄まされている。それは時に、快刀乱麻を断つような趣がある。松下幸之助の言葉には深さがあり、後藤田正晴や大平正芳の発言には決断する人の苛烈さがある。中村哲の寸句は極限状況を経験した人だけが言えるものだ。やなせたかしのように柔らかい中にも芯がある言葉もある。人物と言葉に出会えるのが本書である。
目次
第一部 私の師が遺した言葉(松下幸之助「鳴かぬならそれもまたよしホトトギス」(野田佳彦)
丸山眞男「歴史をつくるのは少数者だ」(三谷太一郎)
石原裕次郎「ようやくオレたちの仲間に入れたな」(峰竜太)
井上ひさし「僕は選考委員を降りないといけない」(野田秀樹)
田部井淳子「エベレストも登りたくて登っただけよ」(市毛良枝) ほか)
第二部 肉親と先達が遺した言葉(水木しげる―「妖怪」と「家族」を愛した漫画家の幸せな晩年(武良布枝(夫人)×尚子(長女)×悦子(次女))
美空ひばり―僕は「不死鳥コンサート」には反対だった(加藤和也)
石原慎太郎―父は最期まで「我」を貫いた(石原延啓)
わが師・阿川弘之先生のこと(倉本聰)
立花隆―私とは波長が合わなかった「形而上学論」(佐藤優) ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くものすけ
ベンアル
hiyu
言いたい放題
-

- DVD
- 極道の紋章 完結編