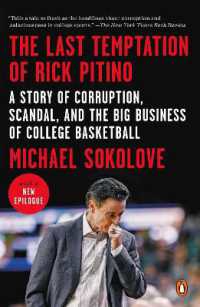内容説明
「この国の成り立ち」を知ることは、現代を生きる私たちが直面する様々な問題の理解に繋がります。本書は、東大、京大、阪大など、一流大学の入試問題から、“歴史のターニングポイント”を問う良問を選んで解説。社会が大きく変化するときこそ、その構造や特質が見えてきます。
目次
第1部 古代(古墳の変遷から国作りの過程が見えてくる(新潟大学)
「日出づる処の天子」に込められた外交戦略(東京大学)
摂関政治は律令体制の完成形?(大阪大学)
中世は「院政」から始まる(東京大学))
第2部 中世(鎌倉時代の幕府と朝廷の関係(東京大学)
後醍醐天皇の理想と現実(大阪大学)
「日本的」な農業の成立(名古屋大学)
貴族の文化から民衆の文化へ(京都大学))
第3部 近世(末期養子が禁じられた理由(大阪大学)
徳川吉宗が直面した物価問題(一橋大学)
時代を先取りした田沼意次の経済政策(京都大学)
「鎖国」下に開かれた「四つのロ」(東京大学))
著者等紹介
相澤理[アイザワオサム]
1973年生まれ。東京大学文学部卒業。長年にわたり、東進ハイスクール・東進衛生予備校講師としてセンター試験倫理対策講座を担当。現在は、通信制予備校「早稲田合格塾」のほか、首都圏の高校で受験指導にあたっている。また、YouTubeチャンネル「ユーテラ」で授業の動画を配信中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ta_chanko
18
日本史は混沌→統制→混沌・・の繰り返し。外圧や危機に臨んで中央集権化・制度化を図るものの、危機が過ぎれば、やがて制度はなし崩しになり、権力も分権化する。現代も終戦から80年ほど経過して政治もぐだぐだになってきているが、一方で対外的な危機も迫ってきており、歴史上繰り返されてきたように、一気に集権化が図られるかもしれない。ぐだぐだな社会のほうが幸せな気もするが‥。2023/10/21
むむむ
3
センター試験に向けてある程度詰め込んだ日本史の知識を手繰りながら読み進めた。 どうしても受験生の時は詰め込むことが優先となっていたが、改めて整理して線にしてもらうことができた。 やはり、中世の始まりが武士の出現ではなく、院政の始まりからというところが印象的だ。班田収授などで中央集権の仕組みを作ったものの、限界を迎えることで、先例を重んじる貴族政治にはそぐわなくなり、ある種の強権である上皇の存在の重要性が出てきたということがよくわかった。2023/11/02
時雨
2
『東大のディープな日本史』シリーズの著者が、東大・阪大など難関国立大学を中心とする日本史の入試過去問を解説。古代・中世・近世の3区分から各4問を取り上げ、歴史のターニングポイントという視点から時代背景を含めて紹介する。〈古代〉三善清行「意見封事十二箇条」の記述から読み解く地方行財政の行き詰まりの原因、〈中世〉承久の乱圧勝で均衡が崩れた朝幕関係、〈近世〉江戸時代の日中交易の特徴と国内産業との関係など、他大学に比べて東大入試出題者の「ディープ」な意識関心が際立つ内容に感じられた。2023年8月初版。2024/09/30
siomin
2
日本史の予備校講師による大学入試問題を通して日本史を解説する新書。「まるわかり」とはいうものの近現代は無いのが気になりますが,読んでいると日本史の発見があります。600年に隋に使者を派遣し律令政治の教えを請うたなど,そうだったのかという記述もあります。まずはざっと読んだうえで,2回目はじっくりと読むと良いと思います。2023/09/29
ハード160
1
歴史の入試問題から、考える事の大切さを知りました。自分も日本史は超得意でしたが、あくまで私立文系なのでこういう切り口で問題を解いていなかったですね。流れというか、歴史を思考することの面白さが詰まった本だと思います。2025/11/16
-
- 洋書
- Decadence