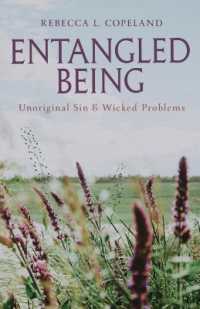出版社内容情報
一辺約3メートル、組み立て式のモバイル住宅「方丈庵」は鴨長明の集大成だった。誰もが知る古典を建築として読み解く新たな試み。
内容説明
たび重なる災害、突然の失踪…そんな「世の無常」を描いた古典『方丈記』は「終の棲家」としての方丈庵を作るまでの「家」の物語でもあった。鴨長明が家にこめた想いをたどりつつ、自分にとって本当に必要なものだけで形づくる「小さな家」の可能性を探る。
目次
第1章 「人と栖」の無常―『方丈記』のあらまし
第2章 鴨長明の生涯
第3章 方丈庵に持ち込まれたモノ
第4章 方丈庵ができるまで―プロトタイプと完成形
第5章 再生の地、日野山
第6章 『方丈記』のルーツ
第7章 方丈庵を継ぐもの―数寄の思想
第8章 江戸期の小さな家―芭蕉・良寛・北斎
第9章 ソローの「森の家」
第10章 現代の「小さな家」
著者等紹介
長尾重武[ナガオシゲタケ]
1944年東京都生まれ。武蔵野美術大学名誉教授。1967年、東京大学工学部建築学科卒業、1972年、同大学院博士課程単位取得満期退学。工学博士。東京大学工学部助手、東北工業大学建築学科助教授を経て、武蔵野美術大学建築学科教授、同大学学長を務めた。専門はイタリア建築史。詩人として『同時代』同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チャーリブ
39
副題は「方丈記を建築で読み解く」。鴨長明が最晩年を過ごした日野山の方丈の庵を建築学の専門家がその思想を含めて分析したもの。方丈庵は移動可能のモバイルハウスと書いてありますが、むしろ組立式の小屋のようなイメージですね。長明は50歳で出家、57歳で日野山に入り、当地で62歳で死没しています。方丈庵は彼にとっては「最期を迎える家」だったわけですが、法華経、阿弥陀絵像、普賢絵像の他に、琴と琵琶、和歌の書物なども大事に置かれていました。彼の最期を看取ったのは音楽と文学だったのでしょうか。2022/10/22
zeeen
4
方丈庵やソローの森の家など本当に必要で大切なものだけに囲まれた簡素で小さな栖の思想には共感。広告に欲望を煽られモノが増え経済の発展ばかりを追いかける現代の風潮は疲れるし、そこに豊かさを見出せるとはなかなか思えない。そして三大随筆である「方丈記」がその200年以上前に書かれた慶滋保胤の「池亭記」に構成、内容まで酷似しているのには驚いた。2024/05/22
あきこ
2
そういえば下鴨神社で鴨長明の方丈庵が展示されていた。そうだったのか、長明は下鴨神社の禰宜の一族だったのか。などと基本的なところからの驚きで始まった。小さな家に住む思想、数寄と信仰に暮らした長明の話から、芭蕉、北斎、ソロー、そしてコルビジェや中村好文、ここまできて自分が惹かれていた小さな家につながり、本書を手にとったことに自分で納得した。お金をかけて人に見せる家を建てる人もいるが、自分の人生をいかに生きるか。家にはその人の人生感が宿るのである。その中の物の選択もしかり。2022/09/16
Go Extreme
1
『方丈記』のあらまし; 建築から読み解く 全体の流れ 遷都と飢餓 災害と無常観 どんどん家が小さくなる 鴨長明の生涯: 新古今和歌集の編纂 突然の出家 方丈庵に持ち込まれたモノ: 臨終の行儀 臨終の場所としての方丈庵 方丈庵ができるまで―プロトタイプと完成形 再生の地、日野山 『方丈記』のルーツ 方丈庵を継ぐもの―数寄の思想 江戸期の小さな家―芭蕉・良寛・北斎 ソローの「森の家」 セルフビルドの家 森の生活とは 現代の「小さな家」 なぜモノにあふれるか 断捨離のすすめ 現代の方丈庵とは 最小の家を考える2022/07/12
どりドリ
1
鴨長明の方丈庵を起点とした小さな家の系譜。読みながら鴨長明はミニマリスト、松茂芭蕉はノマドワーカー、なんて失礼な考えが頭をよぎっていたら最後に断捨離のすすめ、シンプルライフのすすめが出てきて、まあそうなるなと思いつつそれと一緒にしていいのか?とも思うなど。2022/06/18