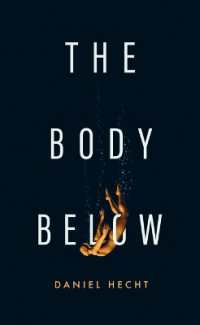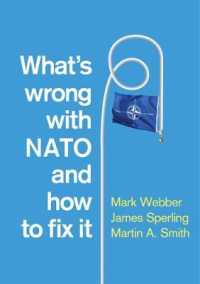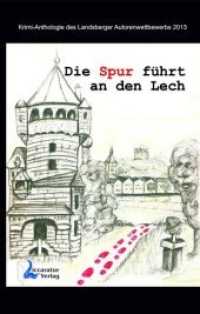内容説明
勘三郎が突然、消えた。玉三郎は幽玄の境地に。海老蔵は團十郎襲名へ。平成歌舞伎へのオマージュ。
目次
第1話 神々の黄昏
第2話 二人阿古屋―歌右衛門から玉三郎
第3話 勘九郎の国盗り物語
第4話 若き獅子たち―海老蔵と勘三郎
第5話 歌舞伎座さよなら公演の向こう側
第6話 澤瀉屋の「恩讐の彼方」
第7話 三つの悲劇
著者等紹介
中川右介[ナカガワユウスケ]
作家、編集者。1960年東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。出版社勤務の後、アルファベータを設立し、代表取締役編集長として雑誌「クラシックジャーナル」ほか、音楽家や文学者の評伝や写真集の編集・出版を手掛ける(2014年まで)。その一方で作家としても活躍。クラシック音楽への造詣の深さはもとより、歌舞伎、映画、歌謡曲、マンガなどにも精通。膨大な資料から埋もれていた史実を掘り起こし、歴史に新しい光を当てる執筆スタイルで人気を博している。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
98
歌右衛門―玉三郎、玉三郎スクールの話は色んなことが腑に落ちた。児太郎と梅枝が阿古屋や揚巻を演じたいと思うにあたり、菊之助がどうしていくのかが気になるところ。玉三郎が阿古屋を演じている時に、同じ舞台に菊之助を置いていたとは知らなかった。勘三郎も海老蔵も、歌舞伎役者としては私はあまり食指をそそられず、そこは作者との好みの別れるところ。勘九郎と七之助は、玉三郎と仁左衛門のもとで助六をできてほんとうに良かったと思う。作者の関西歌舞伎への無関心、そして藤十郎の扱われ方に、腹立たしささえおぼえた。2020/07/02
佐島楓
59
振り返るにはあまりにも近くて痛みを伴う時代・平成。平成に入ってからの歌舞伎は、特に勘三郎さんと串田さんのコクーン歌舞伎に象徴されるコラボレーションによる変化の風が大きいと思っている。今後も実験と変質を繰り返しながら、その時代時代の歌舞伎が出来上がっていくのだろう。守るべき伝統と最先端の技術の融合。面白くならないはずはない。2019/12/01
ぐうぐう
26
平成における歌舞伎史を振り返るにあたって中川右介は、五代目坂東玉三郎、十八代目中村勘三郎、十一代目市川海老蔵の三人の役者に焦点をあてる。この三十年の歌舞伎界を牽引したスターであるとの理由からだが、歌舞伎の変革を担ったのもこの三人であることが、本書を読むとよく理解できる。さらにこの三人の役者に共通しているのは、身近な者の死がその変革の動機となっている点だ。歌右衛門の死により帝政から民主政へとシフトできた玉三郎、(つづく)2019/10/19
ざび
3
恐らく、一番最近の歌舞伎界をまとめた本。 三人に加えて猿之助の立ち位置がわかる。 海老蔵大好きの筆者であるが、勘三郎は同時代なのか克明に演目を記している。2020/05/08
shushu
3
実際の舞台を見ていないのに読んでしまった。生きざまはドラマティックだ。歌舞伎俳優さんの一部はかなり早くに亡くなるね。2020/02/20