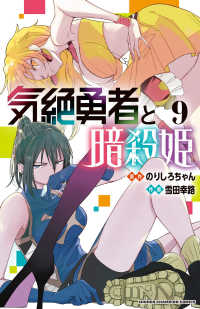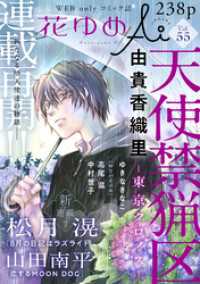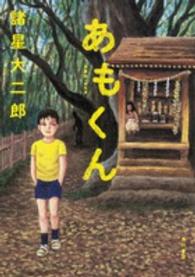出版社内容情報
イラン革命、ソビエトのアフガン侵攻の起こった79年は歴史の大きな転換期だった。歴史に無自覚な日本人は今をいかに生きるべきか。
内容説明
イラン革命、ソ連のアフガン侵攻が起こった年、歴史は大転換した。そのことに気づいた人はどれ程いたのだろうか。自らの歴史を失いつつある日本人は今をいかに生きるべきか。
目次
一九八四年の「アンティゴネ」と二〇〇三年の「アンティゴネ」
戦時の「傷」は暴かれるのを待っている
今さらネオコンだなんて―ネオコンの祖ノーマン・ポドレッツの転変
「一九六八年」を担ったのは誰だったか?
山本夏彦の「ホルモン、ホルモン」
いま何故、四十年前の洗脳テロリスト物語か?
イラク派遣「人間不在の防衛論議」ふたたび
「軽い帝国」が行使する「まだましな悪」
一九七九年春、その時に「歴史」は動いていた
著者等紹介
坪内祐三[ツボウチユウゾウ]
1958年東京生まれ。早稲田大学大学院修士課程修了。「東京人」の編集者をへて評論家に。『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(マガジンハウス)で講談社エッセイ賞を受賞。雑誌「en‐taxi」の編集も手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
61
佐々木敦の批評レクチャー本で推薦する批評本としてあげられていた。中断していたのをやっと読了。特にテーマを決めずに月刊誌に連載されていた記事をまとめたもの。表題の1979年というのは、イランのイスラム革命とソ連のアフガニスタン侵攻という新冷戦期の始まりだったと著者はいう。歴史など存在せず現代が延々と続くだけとされるポストモダンに生きる我々であるが、歴史というものは我々に無関係に続いているという。連載記事は非常にバラバラだで、関連性があるようなないようなもどかしさも感じさせるがそこがポストモダン的か。2018/03/20
白義
5
副題とは裏腹に、1979年の時事はほとんど出てこない、いわば裏テーマのような扱いになっている。強いて語られるのは、政治の季節の風化による大学生のノンポリ化、そしてイラン革命とソ連のアフガン侵攻のみ。終章で触れられるこれらをポストモダン時代の予兆と解釈し、それらに光明を投げ掛ける批評家や思想家たちの各論に、それへの抗いを込める。そういう手の込んだ構成を本書は取っている。平野謙、イグナティエフ、山本夏彦と、語られる著者たちに坪内は微妙な距離感を取りながら共感し、また本書で真似ようとしているのが印象的2012/05/21
さえきかずひこ
4
2008年に一度読んでいたらしいが、そのことをすっかり忘れて再読。2016/11/15
オールド・ボリシェビク
3
論壇誌「諸君!」に掲載された時評である。1979年とはソ連のアフガニスタン侵攻の年。その年を転換的な年であったと、自らの体験などから語り起こすのだが、どうも坪内祐三、こういう時評には不向きなような気がする。「このころ、こういう本を読んだ」という個人的体験が、うまく論旨に直結していかないというか。やはり坪内祐三は学者ではない。だったら何だったのか、という結論はまだ出ていないけどなあ。2025/03/01
静かな生活
1
ポストモダンすら通過してしまったのではないかと思う今日この頃。2022/09/25