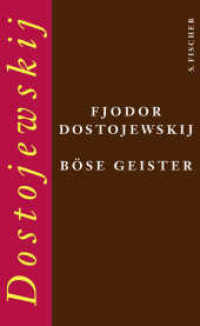内容説明
第二次大戦終結後、東西冷戦構造下で対ソ戦略の中核を担い、世界の情報戦争をリードしたアメリカ。なかでもスパイ=人的諜報のイメージで広く知られたCIAは、その代表格だった。だが冷戦の終焉とともにCIAは対テロ戦略という方向転換を時代に迫られたのだが、「9・11」の悲劇は起きた…。「失われた十年」といわれる九〇年代、なぜCIAは堕ちていったのか?組織とリーダーの在り方の問題をも衝く、気鋭の意欲作。
目次
1章 アメリカ諜報機関の実像
2章 一九九〇年代のCIAと無力な長官たち
3章 敵を失った後の「失われた十年」
4章 CIAとアルカイダの「戦争」
5章 「罪なき者、石を投げよ―そして、誰もいなくなった」
6章 ブッシュの「改悪」
7章 CIAに革命が起きるとき
著者等紹介
落合浩太郎[オチアイコウタロウ]
1962年、東京生まれ。慶応義塾大学大学院法学研究科博士課程中退。東京工科大学コンピュータサイエンス学部助教授。専門は国際政治学・安全保障論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
264
少し古い本だけどCIAの実情についてよくわかる1冊。今やアルカイダって聞かなくなったなぁ。2016/04/14
スプリント
8
国を守るというよりも組織を守ることに四苦八苦している印象です。9.11の真相はいつか明らかになるのでしょうか。(もしくは隠された真相など存在しないのか・・)2015/07/10
きぅり
4
読後、相対性理論のスマトラ警備隊を聴きたくなった。冷戦終わり〜911テロ〜イラク戦争くらいのCIAの迷走っぷりについて書かれてる。情報の解析が追っ付かなくなった成れの果てがイスラム国とか考えると、なかなか面白い。スパイ天国と揶揄されて、情報組織作れやらスパイ防止法作れとか言われまくってる割に911のようなでかいテロ食らってないのは、日本の公安のおまわりさんが優秀だから…?2016/05/15
金沢 衛
4
諜報にかんする、主にCIAの本。ビンラディンが捕まっていないなど古い情報があるが、かなり詳しい。CIAは失敗ばかりしている。2014/02/04
こにいせ
4
ベンジャミン・フルフォードの『911はアメリカの自作自演』論は、妄言だと思うが、本書にあるように、CIAをはじめとする諜報機関の怠慢が招いたという側面はあるかもしれない。本書を読んでつくづく考えさせられることは、現代的な官僚機構そのものの限界である。政治的な思惑でトップの首がコロコロ変わり、各々が地位にしがみついて自浄機能は全くない。日本でもアメリカでも、人間を重視した行政は大事だが、枠組みそのものを見直すべきである。2010/03/16