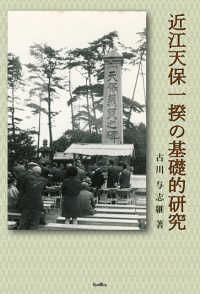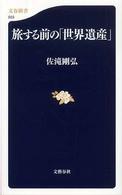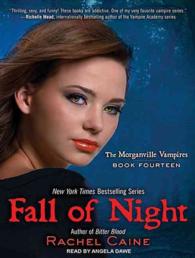内容説明
常に子を見守り、かまう大人たち―幕末・明治に来日した欧米人は、子どもと睦み合う日本人の姿に一様に感嘆の声をあげた。それは江戸時代から続く日本の親子関係そのものだった。近年、日本ではますます教育論議が盛んだが、日本人の教育論好きは江戸時代にまでさかのぼる。この太平の二百数十年間に、江戸開幕の祖・家康以下、儒者、石門心学者、医師など、実に多彩な論者による子育ての書が数多く出現しているのだ。キーワードは「溺愛」だった。
目次
第1章 戦国武将の子ども観からの脱却
第2章 父親像・母親像を示す学者たち
第3章 太平の世の子育て
第4章 教化活動に力を入れた心学者たち
第5章 浮世草子に描かれた子育て
第6章 子育ての工夫さまざま
第7章 下級武士にみる子育て
著者等紹介
中江和恵[ナカエカズエ]
1949年、愛知県生まれ。東京女子大学文理学部日本文学科卒業後、東京都立大学人文学部教育学専攻を経て同大学大学院博士課程単位取得。現在、東京家政大学・和光大学非常勤講師。専攻は教育学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
6 - hey
3
かなり面白かった。家康からはじまり、江戸時代の学者・偉人がどのような子育て論をもっていたのかがわかる。江戸時代の子育ての大きな特徴は子供崇拝。2012/10/25
びっぐすとん
1
明治期、外国人が日本の子育てに感心したという話は聞いたことがあったが(中世ヨーロッパではグルグルまきにして蓑虫みたいに壁に吊るしてたと聞いたこともある)、家康が長男を自害に追いやった経験から、独自の子育て論を持ってたとか意外だった。江戸時代のお父さんは案外イクメンだったんだな。全体的にベタ甘な育児だったようだが、当時も様々な育児論が展開されてたらしい。平成の現在も育児書が氾濫しているところをみると、いつまでたっても育児に正解はないようだ。大人が試行錯誤して悩んでるうちに子供は成長しちゃうからな・・とほほ。2017/01/23
おきぼん
0
子育てに関する記述がこれだけ残っていることに驚いた。 この時代から子育て論を説くのだから、この時代から教育熱心だったのだろう。 自分の子育てに役立ちそうなものは残念ながら発見できなった。2020/11/29
Kiki
0
江戸の子育て事情がよくわかって面白かった。やはり地域で社会で育てるって大事だなと思った。 子どものオムツ外れが1歳半とは驚き。それだけ子どもだけに注力できる環境があったのだろう。父親が主に育てていたのにも驚き。それだけ仕事に没頭しなくても生きていける社会だったのだろう。 子どもが寝付かないとき裸にして肌を触れさせるとよく寝たと記述あり。昔の人の知恵は素晴らしいな。祖母の子育てを思い出した。孫だからと溺愛するだけでなく叱る時は叱り、諭し、立派に育てて貰ったと思う。2018/03/21