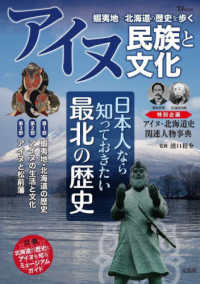内容説明
「君の名は?」親の願いと、生まれた時代がそこには封印されている。
目次
第1章 名前、この深遠なるもの
第2章 名前の源泉―古代文化の多様性
第3章 名前の権威―武家社会の支配力
第4章 名前の革新―近代化の行方
第5章 女性の名前―長かった日陰の歴史
第6章 名前の人気―大正の「ハナ」から平成の「結衣」まで
第7章 名前と法律―親の執念、子どもの迷惑
著者等紹介
紀田順一郎[キダジュンイチロウ]
1935年神奈川県横浜市生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業。近代社会思想史、書物論を経て、現在はコンピューター関連のメディア論などを手がけるかたわら、古書ミステリを発表している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAN
12
名前をつける。人間の基本的な営みだと思うし、単純に親の希望とか、愛の結果として命名があるのだろうけれど、歴史に刻まれた「なまえ」はそう単純なものではない。だいいち、今の日本人の名前のつけかただって、明治以後に決まってきたのだし、だいいち記録にのこっていない人々の名前はその時代でどんな事情でつけられたのか、その真意をさぐるのは難しい。そしてその名前が人の人生を規定してしまうこともあると考えると、不思議な、しかし厳粛なものだと思っった。2022/12/05
manabukimoto
3
名前をつける、という行為が普遍的に行われてきたのではないということがよく分かる。 元々は地名やら官職名やらを付けていたのが、唐風の「二字」漢字の広がりで多様性を得る。ややこしいのは「実名敬避」の習慣。名前は霊魂にくっつくもので、軽々しく相手の名前を言ってはいけないという習慣。中国由来かと思いきや世界中であるらしい。 面白いのは武士が自分の権威性を保つために敢えて難読の名前を付けたがったとのこと。「容敬=かたたか」だったり。キラキラネームを笑えない名前への歪な拘りはずっとあったのだろう。 石川県立図書館蔵書2025/01/31
めいが
2
明治創姓のとき、それまで姓を持っていた人(家)は1割だったという大騒動を知って驚いた。しかも急かされたんだろうな。そりゃあ佐原、浜地、魚シリーズにもなるよね。2024/04/22
tacacuro
2
時代とともに、名前のあり方は変遷してきている。家という考え方は残しつつも、氏名をより「個人」を識別するものとして捉え直すことはできるんじゃないか。「選択的夫婦別姓」を主張するよりも、「原則生涯同一氏名」論の方が建設的だと思う。いずれにせよ、別姓夫婦の子どもの姓をどうするかがが論点となる。いっそこれからは、日本でもラテン圏のように、氏を両親からそれぞれ引き継いで、2つの氏を登録できるようにしてはどうだろうか。2018/02/23
うたまる
2
日本人の名前についての論考。一つ一つのトピックがなかなか面白く、特に一郎次郎というような出生順を表す名前は日本だけの習慣だと知り驚く。また中華圏の俗信である辟邪(故意に汚い名前を付け魔除けとする)では、○○丸や○○麻呂は便器の”おまる”の意であることに衝撃を受けた。朝鮮では”犬の糞”という更にえげつない名前もあったとのこと。改名についてでは、我々が憧れるような由緒ある難字の名前の人が、逆に平凡な名前に変えたいと願っていることに苦笑う。まあ、言われてみれば流行のキラキラネームも大人になれば変えたくなるよな。2016/04/24