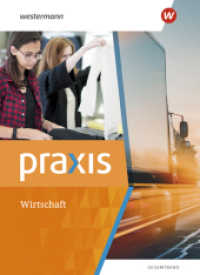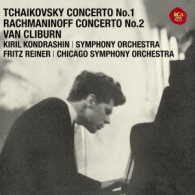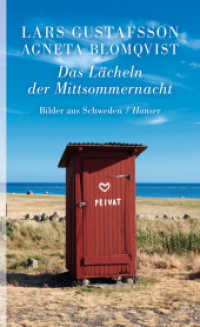出版社内容情報
女性で初めて芥川賞を受賞した中里、晩年になり代表作『秀吉と利休』をものにした野上。二人の作家の豊かな想像力を育んだ日常の記録
女性作家の名随筆のアンソロジー、第10巻は昭和を代表する女性作家である中里恒子と野上彌生子。選者・小池真理子氏は「時雨の記」で中里文学に惚れ込んだ。今回全随筆を読み「思った通りの人だった」と言っている。あまり出歩かず、家事や園芸にいそしみ読書と数少ない友人との深い交わりを愛しんだ作家の随筆は、読めば読むほど豊かな心持になれる。野上彌生子は軽井沢の山荘での独居を好んだ、というところに小池氏は親近感を持ったという。焦らず弛まず大器晩成の文学者人生を歩んだ人、というイメージの作家だが、小池氏のお薦めは小品「カナリヤ」。戦時下の乏しい食糧事情のなか、よれよれのカナリヤをひきとって育てる話だ。この巻で、今は作品入手のしにくい二人の女性作家の、美しい日本語と深い教養に裏打ちされた思索、暮らしの愉しみ方をぜひ味わってほしい。
内容説明
中里恒子の筆でよみがえる小さきもの、忘れられがちなものの煌めき。時代と一線を画しながら学びを極め自然を愛惜した野上彌生子の人生の充実。
目次
中里恒子1 日々の楽しみ
中里恒子2 旧友たち
中里恒子3 本と執筆
中里恒子4 おんならしさ
野上彌生子1 山荘暮らし
野上彌生子2 作家の思い出
野上彌生子3 同時代人へ
野上彌生子4 山姥独りごと
著者等紹介
中里恒子[ナカザトツネコ]
1909年(明治42年)12月23日、神奈川県藤沢市に生まれる。1922年(大正11年)紅蘭女学校(現・横浜雙葉学園)に入学する。1923年(大正12年)9月1日、関東大震災が起こり、紅蘭女学校焼失。半年休学し、川崎高等女学校に編入学。25年、卒業。1928年(昭和3年)処女作「明らかな気持」が文藝春秋社刊「創作月刊」6月号に掲載される。1939年(昭和14年)2月、「乗合馬車」「日光室」が第八回芥川賞に選ばれる
野上彌生子[ノガミヤエコ]
1885年(明治18年)5月6日、大分県臼杵町(現・臼杵市浜町)に生まれる。1900年(明治33年)上京し、叔父・小手川豊次郎方に寄宿。明治女学校普通科に入学。1903年(明治36年)明治女学校普通科卒業、高等科に進む。1906年(明治39年)3月、明治女学校高等科を卒業。1907年(明治40年)2月、夏目漱石の指導で「縁(えにし)」を「ホトトギス」に発表する。1911年(明治44年)9月、「青鞜」創刊に社員として関わるが、翌月退社
小池真理子[コイケマリコ]
1952年、東京都生まれ。成蹊大学文学部卒業。96年、『恋』で第114回直木賞を受賞。2006年、『虹の彼方』で第19回柴田錬三郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
吉田あや
ぐっちー
どら猫さとっち
みみずく
圓子
-

- CD
- 東山奈央/off