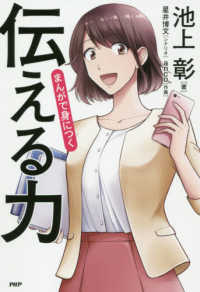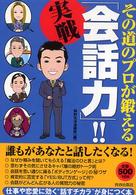- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
宇宙――人智を超えた漆黒の空間で、飛行士たちは何を考えたか。全日本人宇宙飛行士への取材を敢行した史上初のノンフィクション。
内容説明
歴代12人の日本人宇宙飛行士はそこで何を見たのか―。総力取材で明らかになる、宇宙体験のすべて。
目次
1 この宇宙で最も美しい夜明け―秋山豊寛の見た「危機に瀕する地球」
2 圧倒的な断絶―向井千秋の「重力文化圏」、金井宣茂と古川聡の「新世代」宇宙体験
3 地球は生きている―山崎直子と毛利衛が語る全地球という惑星観
4 地球上空400キロメートル―大西卓哉と「90分・地球一周の旅」
5 「国民国家」から「惑星地球」へ―油井亀美也が考える「人類が地球へ行く意味」
6 EVA:船外活動体験―星出彰彦と野口聡一の見た「底のない闇」
7 宇宙・生命・無限―土井隆雄の「有人宇宙学」
エピローグ 宇宙に4度行った男・若田光一かく語りき
著者等紹介
稲泉連[イナイズミレン]
1979年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
94
宇宙から帰ってくると世界観は変わるのか?そんなインタビュー集 。当たり前だが大きく変わるらしい。我々が初めて海外旅行へ行った後と似ているのか?否、それ以上なのだろう。考えてみれば当たり前なのだが。地球には重力があり、土がある。飲水も生命が育んだ結果のもの。それらは全て蒼い地球が育んだもの。そしてそれを得て人類が科学技術により宇宙に行く為に注ぎ込んだ叡智。加えて宇宙には国境や所有物の概念はない。また、宗教観はどう絡んでくるのか?等、遠からずある程度の数の人類が宇宙へ旅立つことが出来る時代に現在迄の変遷を表す2020/12/20
ぶんこ
66
凄く面白かったです。立花隆さんや向井さんの本も読んでいたのですが、恥ずかしながら宇宙ステーションが地球から僅か400キロ(東京ー大阪間)しか離れていないとは知りませんでした。故に一部の宇宙飛行士は「出張届」を出し「地球周回、低軌道」と書く!一度は宇宙にと思いつつ、私の年代では無理なのですが、読み友さんの感想に「あの世への寄り道で行く」とあって、その手があった!と大拍手。本当は船外活動を実感したかったけれど、寄り道の時に実感できるかな?若田さんが「美しい惑星を故郷とよべてラッキー」とあり、まさにラッキー。2020/04/16
けんとまん1007
64
読み終えたあと、星出さんのニュースが飛び込んできた。共通しているのが、宇宙から地球を見たことから、人類・ホモサピエンスとしての仲間という視点。そこに立脚すると、今、この星で起きている戦争・諍いなどが別次元のことと映るということ。視座をどこに置くかの重要性が痛感させられる。それと、未来への視点だ。2021/04/23
hatayan
56
日本人の宇宙飛行士12名に宇宙体験を聞き取り。スペースシャトルの事故を目撃してそれでも宇宙に行く意味はあるかと自問した野口聡一。人は自分よりも大きな何かとつながっていないと不安になる存在だと宇宙で学んだ大西拓哉。宇宙に行くことの成果が問われる現在にあって、宇宙飛行は出張の延長と言い切る金井宣茂。既に4回宇宙に飛んだ若田光一。1990年に秋山豊寛が宇宙を初めて飛んでから30年近く、宇宙飛行士の意識や役割も大きく変わりました。 作中を通して、立花隆の『宇宙からの帰還』に敬意を払っていることがわかります。2020/02/19
kawa
43
EVA(船外活動)は、宇宙船中の体験とは全く異なるのだそうだ。そこでは、『無限というものを直接、この目で見た』(土井隆雄氏)『本来は〈地球の一部〉であるはずの自分の光景が不思議(略)そして感じたのは〈絶対的孤独〉』(野口聡一氏)…、哲学的?禅の悟り?頷けないでもない境地。アメリカ飛行士のノンフィクションである立花隆氏「宇宙からの帰還」にインスパイアされ、日本人宇宙飛行士に対して試みる本書。『自分は地球に生かされる』、宇宙社会からの視点、実に夢多くエキサイティング。閉塞状態の地球を救う可能性を大いに感ずる。2020/02/04
-
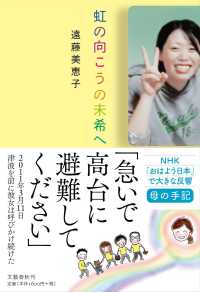
- 和書
- 虹の向こうの未希へ