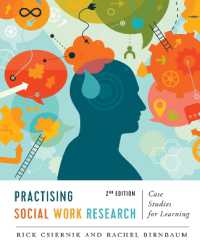出版社内容情報
VR内での体験を脳は「現実」として処理する。人類史上初めての刺激の数々に、我々の脳は対応できるのか。VR研究のトップが語る。◆心理学?テクノロジー、仮想現実の最前線◆
・VR内での体験を、脳は現実の出来事として扱ってしまう
・VR内で第三の腕を生やしたり、動物の身体に?移転?しても、脳はすぐさまその変化に適応し、新たな身体を使いこなす
・イラク戦争後、?バーチャル・イラク?を体験するVR療法により、PTSDに苦しんでいた二〇〇〇人以上の元兵士が回復した
・VRで一人称視点の暴力ゲームをプレイすると、相手が仮想人間だとわかっていても生々しい罪悪感を覚える
・仮想世界で一日過ごすと現実と非現実の違いがわからなくなる
・VRユーザーの身体や視線の細かな動きは、正確にデータ化できる
・そこからその人の精神状態、感情、自己認識がダイレクトに読み取れる
【目次】
■序 章 なぜフェイスブックはVRに賭けたのか?
私は二〇年にわたり、認知心理学の観点からVRを研究してきた。今のVRブームは、
二〇一四年にフェイスブックが「オキュラス」を二〇億ドル超で買収したことから始
まったが、実はその数週間前、マーク・ザッカーバーグは私の研究室を訪れていた。
■第1章 一流はバーチャル空間で練習する
VR内での経験は、現実の経験と同様の生理学的反応を脳にもたらす。VRは人類の
歴史上、最も強い心理的効果を持つメディアなのだ。では、これを学習に応用したら
なにが起きるだろうか。NFLのチームで行った実験は、驚愕の結果をもたらした。
■第2章 その没入感は脳を変える
VRでは一人称視点の暴力ゲームを作らない――ゲーム開発者は早々にこの結論に至
った。ゲームであってもVR内の殺人はあまりに生々しく、罪悪感を残すからだ。V
Rは脳へ強烈な影響を与える。仮想世界で二五時間過ごした男にもある変化が起きた。
■第3章 人類は初めて新たな身体を手に入れる
特殊な?鏡?を使えば、人間の脳はいとも簡単に仮想の身体を自分自身だと思いこむ。
これをVRと組み合わせれば、年齢や人種の異なる人間はもちろん、別の動物の身体
に移転することも可能だ。人類史上初めての事態に、我々の脳は対応しきれるのか?
■第4章 消費活動の中心は仮想世界へ
宇宙から海底まで、誰でも簡単に旅ができるVRが普及することで、世界の消費活動
は一変する。既に仮想世界で遊ぶための衣服・不動産・船などにあらゆる階層の人々
が多額を投じ、巨大な経済圏が生まれている。これを軽視すると未来を見誤るだろう。
■第5章 二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト
同時多発テロ後、多くの人がPTSDに苦しんだ。治療にはトラウマの再現が有効だ
が、本人の記憶に頼る従来の手法ではあまり効果はなかった。そこである専門医は、
テロ当日を緻密に再現したVRを作製。患者を再度、九月一一日のNYに送り出した。
■第6章 医療の現場が注目する?痛みからの解放?
重度のやけど患者は治療で想像を絶する激痛を味わう。それはどんな鎮痛剤も効かな
いほどだ。だが治療中の患者にあるVRソフトをプレイさせると、劇的に痛みが和ら
ぎ、脳の活動にも明確な変化が見て取れた。このVR療法の登場に衝撃が走っている。
■第7章 アバターは人間関係をいかに変えるか?
ユーザーの細かな表情や動きを仮想世界のアバターに反映させる技術は急速に進化し
ている。誰もが仮想空間で交流し、通勤や出張が不要になる日も来るはずだ。だがあ
らゆるアバターは心理学に基づく印象操作を駆使して、表情や行動を偽装するだろう。
■第8章 映画とゲームを融合した新世代のエンタテイメント
ハリウッドではゲーム業界出身者が集まり、VRを用いた全く新たな物語作品を作り
始めている。VRは没入感と引き換えに、一本道のストーリーには向かないという弱
点がある。解決策として彼らが注目するのは、AIを用いた?ストーリー磁石?だ。
■第9章 バーチャル教室で子供は学ぶ
ハーバード大学では、一九世紀の町をインタラクティブに再現したVRを制作。当時
の世界にタイムスリップして科学を学ばせる「VR社会見学」を中学生に体験させた。
結果、生徒たちの学習意欲は大きく向上。VRは教育の世界も劇的に変えていく。
■第10章 優れたVRコンテンツの三条件
かつては一部の専門家にしか扱えなかったVRも、今では誰でも簡単に入手できるよ
うになった。既存のメディアとは全く異質で、測り知れない力を秘めたこの技術は、
人類にとって諸刃の剣だ。その制作者は三つのルールを必ず守らなければならない。
ジェレミー・ベイレンソン[ジェレミー ベイレンソン]
著・文・その他
倉田 幸信[クラタ ユキノブ]
翻訳
内容説明
VRを新しいゲームや映画の一種だと思っていると、未来を見誤る。このメディアはエンタテイメントだけでなく、医療、教育、スポーツの世界を一変させ、私たちの日常生活を全く新たな未来へと導いていく。その大変革を、心理学の視点から解き明かそう。現在のVRブームは、クラウドファンディングから始まった小さなVR機器メーカー「オキュラス社」をFacebookが巨額で買収したことから始まった。世界を驚かせたその買収劇のわずか数週間前、マーク・ザッカーバーグは本書の著者の研究室を訪れ、最新のVRを自ら体験していた。そこでザッカーバーグが味わった衝撃が、この本には詰まっている。
目次
なぜフェイスブックはVRに賭けたのか?
一流はバーチャル空間で練習する
その没入感は脳を変える
人類は初めて新たな身体を手に入れる
消費活動の中心は仮想世界へ
二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト
医療の現場が注目する“痛みからの解放”
アバターは人間関係をいかに変えるか?
映画とゲームを融合した新世代のエンタテイメント
バーチャル教室で子供は学ぶ
優れたVRコンテンツの三条件
著者等紹介
ベイレンソン,ジェレミー[ベイレンソン,ジェレミー] [Bailenson,Jeremy]
スタンフォード大学教授(心理学、コミュニケーション学)。同大学でバーチャル・ヒューマン・インタラクション研究所を設立し、所長を務める。ノースウェスタン大学で認知心理学の博士課程を修了。VR(バーチャル・リアリティ、仮想現実)研究の第一人者。現在のVRブームの発端となったフェイスブックによる「オキュラス」買収直前には、マーク・ザッカーバーグCEOがベイレンソン教授の研究室を訪れ、教授が制作した最先端のVRを視察していた。心理学者としてキャリアを始め、人々のコミュニケーションについて研究を行う中で、VRが人の心理や行動に大きな影響を与える、従来にないまったく異質なメディアであることに注目。以後、VR心理学の専門家となる。
倉田幸信[クラタユキノブ]
1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。朝日新聞記者、週刊ダイヤモンド記者、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集者を経て、2008年よりフリーランス翻訳者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミライ
Miyoshi Hirotaka
Kentaro
shikada
スプリント
-

- 電子書籍
- ニセ妻になったらクールな御曹司に溺愛さ…