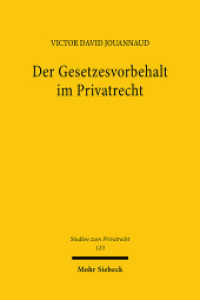出版社内容情報
“事故”で国土を失い、世界各地の難民キャンプで暮らす日本人。確かな情報も希望もなき異邦の地で、「日本人として」生きる人々。
内容説明
国土を失っても日本人は日本人たりえるのか?“あの事故”で居住不能となった日本。十年前に描かれていたポスト・フクシマの世界。
著者等紹介
勝谷誠彦[カツヤマサヒコ]
1960年兵庫県尼崎市生まれ。早稲田大学第一文学部文芸科で作家・平岡篤頼に師事する。在学中『早稲田文学』に小説『きんぎょ』を発表しデビュー。企業勤務を経て写真家、文筆家。食や旅に関する著作を多く上梓する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
C-biscuit
12
図書館のリサイクル本。2つの話が載っているが、人物などのつながりはなく、事故後の日本に残った人の日常と難民として国外に出た人の暮らしが書かれている。事故というのが共通であり、詳細な説明はないが、どうも原発事故のようである。東日本大震災の前の本であることを思うとリアリティのある内容にも感じるが、チベットに難民とし行くのはそもそもどうなのかとも感じる。日本人が日本人たる理由というのは、世代を超えていった場合にどのように伝わって行くのかを考えさせられる。人種ではなく継続した文化かとも思うが、変わるものでもある。2018/05/10
それいゆ
5
本の帯には「原発事故で国土を失った日本人のアイデンティティーを追究した作品。10年前に描かれていたポストフクシマの世界。」というふうに書かれています。「勝谷誠彦は、すごい小説を描いていたのだな。ぜひ一度読んでみたい。」と図書館に希望を出して購入してもらい、この本を手にしました。わざわざ買ってもらって申し訳なかったという気持ちでいっぱいです。すみませんでした。チベット民族や杜氏の話がだらだらと続き、原発事故がかすんでいます。文章が独りよがりで、物語の展開が分かりにくくて、読みづらかったです。2011/11/19
Nobuchika Hotta
5
勝谷誠彦さんの有料メルマガを購読しています。一年365日、一日も休むことなく送信され、日々のニュースを氏ならではの感性で両断されます。日々、メルマガを読みながら敬服しています。「お母さんに何が起きたかは、私がすべて知っている。私が知っていれば、私の記憶は子供につながるから。お父さんが知らなくても、お母さんにおきたことを、私の子孫が続くかぎり忘れないから」との言葉が一番印象的でした。2011/08/29
takao
3
ふむ2024/12/18
つくし
3
離散や移民を意味するというディアスポラ。それを冠した日本の小説には何が描かれているのだろうと気になり手にとってみました。2話収録、移民となった話と、離散してしまった話だった。とらわれているのは土地に対してなのか、国民という自負に対してなのか、そういった内外にある「認識」なのか。反して、「所属」という意識は何をもって自覚されているのか、考えさせられました。ユダヤ人が互いをそれと認識できることの強かさにどきりとする。2024/03/04