出版社内容情報
日本一の宮大工集団・鵤公舎が木造寺院を建立するプロセスを、職人たちの語り、写真と図でわかりやすく解説した、後世に残したい一冊。
内容説明
法隆寺最後の宮大工・西岡棟梁の後継者、小川三夫棟梁が率いる鵤工舎。東北最大規模の寺院本堂建立のために、一流職人のドリームチームが集結。世界最高の技の秘密が初めて明かされる。
目次
第1章 棟梁・小川三夫の考える本堂
第2章 材木
第3章 基礎
第4章 表具師
第5章 左官
第6章 建具
第7章 屋根瓦
第8章 本堂再建
著者等紹介
塩野米松[シオノヨネマツ]
昭和22年、秋田県生まれ。東京理科大学理学部卒業。虫プロを経て独立、著述業に入る。日本のアウトドアライターの先駆者となる。小説では連続四回の芥川賞候補に。職人の聞き書きでも多大な業績をあげている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
265
若手育成にもユニークな一家言を持つ宮大工の棟梁、小川三夫さんの、「仕事」を丁寧に描く。壁が直線に見えるために、わずかに中央部を盛り上げて塗る左官職人。壁に金箔を貼るのに本金(二十四金)だと退色が少ないが、中金(真鍮を塗っているモノ)だと酸化して百年で黒ずんでしまう、など、こだわり、「本物」の世界が垣間見える。2025/01/05
石油監査人
31
鵤(いかるが)工舎とは、法隆寺の宮大工の小川三夫が設立した寺社建築専門の建設会社です。伝統的な技法を使った寺院の改修、再建、新築に定評があり、この本では、宮城県角田市にある長泉寺の本堂の再建工事の様子が、写真や図、棟梁から住職まで9人の関係者へのインタビューを通して描かれています。例えば、美的な観点から筋交いを一切用いず、貫(ぬき)と呼ばれる手法で木材を接合し、瓦の重みで建物を押さえつけて耐震強度を高めるなど、普通の木造建築とは異なる独特の設計思想は興味深く、また、完成した建物は飛鳥風でとても美しいです。2024/12/02
booklight
29
宮城県長泉寺の本堂建立にかかわった方々の話をまとめたもの。棟梁の小川さんを中心に、材木、基礎、表具師、左官、建具、屋根瓦の職人に話を聞く。小川さんがきっちり図面を引いてしっかりした仕事をするので、その緊張感がほかの職人にも伝わっている。とはいえみんな何か響くようなコメントをするのかといえば、そんなこともない。そこがまたリアル。100年持つかと言われて、基礎の鉄骨やのりが持つわけではない、というのが現実。しかし、寺のイメージをデザインして、職人まで手配するって、棟梁ってやっぱりすごい仕事だなと思う。2023/04/01
へへろ~本舗
5
法隆寺・薬師寺の棟梁だった西岡常一師の内弟子の宮大工,小川三夫氏が建立した長泉寺の記録である。図面掲載の他に本堂・材木・基礎・表具師・左官・建具・屋根瓦の章に分かれそれぞれ携わった人々の技と知恵、勘と工法、そして思いについて記載されている。何しろ考え方の規模が違う、何百年、千年の単位で考えているのだ。経済が厳しくなり、材木(樹齢数百年越え)などの入手も困難になっているのでこんな規模のお寺の建立は技術の伝承も含めて今後難しくなってくるだろう。角田市にある長泉寺、暖かくなったら見に行こうと思う。2021/03/05
ZEPPELIN
5
神社仏閣の建立に携わった人たちへのインタビュー。ただ建てるというのではなく、いかに美しく見せるか、そして建物自体をどれだけ長くもたせるか。台風や地震も考慮して、目に見えない部分でも絶対に手は抜かない。特に心に残ったのは、全体から部分へという流れで作業するということ。完成図・全体像が頭で描けているからこそ、細部にもこだわることが出来る。その習得には少なくとも10年以上かかるなんて聞くと、職人さんの世界はやはり大変である。もっとこの分野について学んでみたい2015/02/28
-
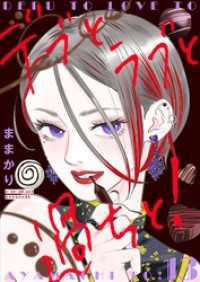
- 電子書籍
- デブとラブと過ちと!【描き下ろしおまけ…
-

- DVD
- うさぎちゃんでCue!!(1)





