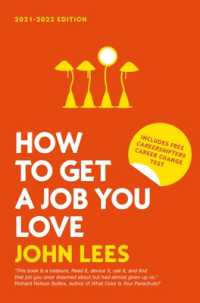出版社内容情報
戦局愈々のぞみない昭和二十年、東京根津の団扇屋の主人が欠かさず綴る驚倒・讃嘆すべき日記帖。十七年の歳月をかけた執念の大作
内容説明
戦局いよいよ見通しのない昭和二十年春のこと、東京根津に団扇屋を営む一市民が、日記を綴りはじめる。その驚倒・讃嘆すべき戦下の日常の細密な叙述には、一片の嘘もなく、まじりっけなしの真実のみ。耐乏に耐乏かさねつつ、人々は明るく闊達そのもの。この奇妙な時空は、悲惨ながら郷愁をさそわずにおかない。そして敗戦、日記はつづく。占領軍は、忌むべき過去を断つべく日本語のローマ字化をはかる…。国家、市民、そして国語とは何なのか?待つこと久し、笑いと勇気、奇想と真率。記念碑的名著ついに完成。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
56
敗戦間近い昭和20年4月から戦後数年間にかけての出来事を山中信介の日記という形で描いた作品。終戦間近の混乱の中闇成金や軍部に媚びる町会長など闇の部分が描かれ、そういった社会的混乱は敗戦後も続くが、この作品の一番のテーマは、後半信介が関わる国語国書問題。なぜ日本語を死滅させてはならないのか。それは、戦争には負けたけれどもなくしてはいけないものがあり、それを守り抜かなければならないということを真剣に考えるということだ。2024/07/26
さんつきくん
14
780pの長編。文庫本にすると上下巻に別れる。旧字体で書かれているのも特長。井上ひさし作品特有の脱線はあれど、下ネタが全くない。東京・根津に住む団扇職人で主人公の山中の日記を通し戦時中・戦後の日本や東京近辺が描かれていて興味深い。戦時中はトラックを買い運送業をしていた山中。ガソリンのやりくり、空襲警報に変に冷静でいられる主人公が印象的である。戦後は山中の娘達(東京セブンローゼス)が大活躍する。日本語の危機を救うのだ。アメリカのお偉いさんが漢字撤廃論を主張し、山中は翻弄される。3度も獄中に入る羽目に。2017/05/04
やまねっと
9
本当に長い本だった。戦時下での市民の生活を著した小説だと思ったら、3分の2くらい読んだところで急に展開が変わり、作者が言いたかったのはそこだったのかという話に変わっていく。それは日本語のローマ字化になるところの話で、事実であるのかは判らないが、当時もそれと似たことがあったのだろうと推察する。3回目に牢屋に入れた後の全ての出来事の謎解きはとても読んでいてハラハラしワクワクした。 旧仮名遣いで書かれた本だが、読みにくいが、慣れれば容易に読めた。770頁もなる本書は長いが多くの人に読まれるべき作品だと思った。2021/08/17
yasumiha
7
戦争終盤の昭和20年4月から、戦後昭和21年4月までの1年間を主人公山中信介の日記と言う手法で描写している。連合軍側の日本語、漢字廃止論と言う計画を知り得た信介と、それを取り巻く「東京セブンローズ」の面々が行動を起こす。東京根津の団扇屋の主人である信介の真面目だが剽軽、少し斜に構え、洒落っけがあるところが何とも言えない。戦中戦後の暮らしは決して余裕はないが、信介の日記は人々の暮らしが闊達に生き生きと描かれており、当時の雰囲気を肌で感じる気配がした。「漢字」の功罪も理解でき、名作中の名作である。2025/05/27
コロチャイ
7
長い長い小説だった。しかし感動の一言だ。戦時中の宮永界隈の生活や風情、そしてつらく長い統制の日々、理不尽な戦争による喪失など、山中信介は生きてきた。この生活日記が素晴らしい。そして後半の日本語をめぐるアメリカ人将校との激論。面白かった。特に一人称に対する日本語の多様さ、私自身誇りに思った。とにかくすごい小説だと思うし、井上ひさしの戦争に対しての鎮魂歌的な作品だと思った。2022/02/15