出版社内容情報
2020(令和元)年、91歳を迎えた末和海の人生は、時計、とりわけ機械式時計(メカニカルウォッチ)と共にあった。末の姿勢は、すでに10代で確立されていた。それは、「理論と技能技術の両面から機械式時計のすべてに精通する」ことだった。
日本で初実施の「アメリカ時計学会・公認上級時計師(CMW)認定試験」に、1954(昭和29)年、若干27歳で合格した末は、自身の姿勢を機械式時計に関する高度なアフターメンテナンス、時計メーカーでの斬新な製品開発という「現場」で貫くだけにとどまらず、人材育成の面でも若き後進に多大の影響を与え続けている。その末が、自身の91年に及ぶ人生の道のりをつまびらかにすることで、「今、時計師の存在が必須である」ことの意味を訴える。機械式時計の製作、アフターメンテナンスを志す人、そして機械式時計を「思い出の一品」とする全ユーザー必読の書。
内容説明
2020年、91歳を迎えた未和海の人生は、時計、とりわけ機械式時計(メカニカルウォッチ)と共にあった。末の姿勢は、すでに10代で確立されていた。それは、「理論と技能技術の両面から機械式時計のすべてに精通する」ことだった。日本で初実施の「アメリカ時計学会・公認上級時計師(CMW)認定試験」に、1954(昭和29)年、弱冠25歳で合格した末は、自身の姿勢を機械式時計に関する高度なアフターメンテナンス、時計メーカーでの斬新な製品開発という「現場」で貫くだけにとどまらず、人材育成の面でも若き後進に多大の影響を与え続けている。機械式時計の製作、アフターメンテナンスを志す人、そして機械式時計を「思い出の一品」とする全ユーザー必読の書。
目次
はじめに―なぜ今「時計師」が必要なのか
第1章 幼少期の時計と模型を相手の一人遊び
第2章 学生時代の「頼まれ時計店」が大繁盛
第3章 時計店開業、日本初で「時計師」試験に合格
第4章 サラリーマン稼業に転職
第5章 83歳で第一線から身を引く
終章 最後のミッション―行動、挫折、そして将来へ
著者等紹介
末和海[スエカズミ]
1929(昭和4)年、大阪府堺市に生まれる。5、6歳頃の幼年期から機械式時計に強い興味を示し、中学校時は独学で修理技能技術を磨く。1945(昭和20)年、大阪工業専門学校(現・大阪府立大学工学部の前身)精密機械科進学後は、技術技能と理論の両面で時計学研究に励む。1949(昭和24)年、「日本時計師会」の前身、「日本時計学会関西支部」の発足に参加。1954(昭和29)年、日本で初実施されたアメリカ時計学会「公認上級時計師(CMW)」試験に25歳で合格。1967(昭和42)年、労働省中央技能検定委員会学識経験者委員に就任。以降、2006(平成18)年まで足掛け40年間にわたり委員を続ける。1970(昭和45)年、千葉で開催された「技能五輪国際大会時計修理職種競技」のショップマスターを務める。1985(昭和60)年、労働大臣表彰受賞。2013(平成25)年、再興した日本時計師会の初代会長に就任。2014年、34年ぶりにCMW試験を再開。翌15年、1名の合格者が誕生。2016年には本邦初の初級時計師(CW)試験を開催、5名の合格者が誕生した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buchi
-
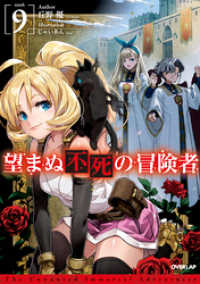
- 電子書籍
- 望まぬ不死の冒険者 9 オーバーラップ…
-

- 和書
- 測量学詳説 - 応用編






