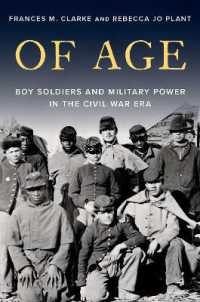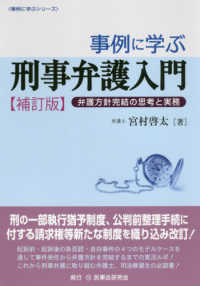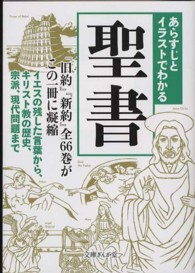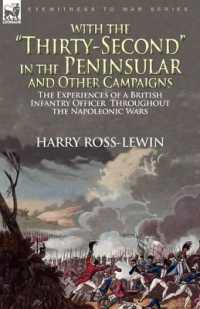出版社内容情報
咸臨丸での渡米、不偏不党の新聞『時事新報』創刊、そして慶應義塾の創設と教育改革――。開国に伴う体制一新の時代、勝海舟、北里柴三郎、川上音二郎ら傑物との交流と葛藤の中で、国民たちの独立自尊を促し、近代日本の礎を築いた福澤諭吉の知られざる生涯。
内容説明
咸臨丸の渡米目的は、外交使節団の護衛ではなかった。福澤諭吉の生涯を、現代の知の巨人・荒俣宏が膨大な資料を渉猟して著した、評伝小説の決定版。近代日本の父、福澤諭吉最後の「自伝」。
著者等紹介
荒俣宏[アラマタヒロシ]
1947年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、日魯漁業(現マルハニチロ)に入社。コンピュータプログラマーとしてサラリーマン生活を送るかたわら、紀田順一郎らとともに雑誌「幻想と怪奇」を発行、編集。英米幻想文学の翻訳・評論と神秘学研究を続ける。1970年、『征服王コナン』(早川書房刊)で翻訳家デビュー。1987年、小説デビュー作『帝都物語』で第8回日本SF大賞を受賞。1989年、『世界大博物図鑑第2巻・魚類』でサントリー学芸賞受賞。近年は京都国際マンガミュージアム館長も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
151
久々の荒俣 宏です。福澤諭吉の評伝というよりも、福澤諭吉エピソード集といった感じです。上巻、一気読み、続いて下巻へ。トータルの感想は下巻読了後に。 https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000015608/2024/04/10
KAZOO
97
福沢諭吉の自伝を荒俣宏さんが書き直したものです。「ミステリマガジン」連載の時には読んでいなかったのですが、まとまって出版されたので読んでみました。「福翁自伝」もはなし言葉なのですがそれよりも読みやすく、著者の荒俣さんが登場したりはたまた諭吉の分身のようなものが出てきたりして楽しめます。荒俣さんのしゃべっている様子が目に浮かびます。「時事新報」を出版したりしているところで上巻は終了です。2024/02/21
ばんだねいっぺい
24
希代の博覧強記、荒俣先生の面目躍如にして畢生の一冊。福沢諭吉の憑依ぶりに震える。エピソードにいちいちひっくり返るが、咸臨丸がやっぱりいちばん、がーーんと脳みそをダイレクトで殴打された気分になった。2024/12/28
ちゃま坊
15
若者たちが尊王攘夷にとりつかれていたころ、学問と出版にニッチを見つけた諭吉青年。先見の明はあった。これからは西洋の学問の時代だ。今までの世襲による古い仕組みは変わる。と明治維新のときに思ったか。ドラマ「坂の上の雲」を観ていたら、好古少年も「学問のすすめ」を読んでいた。1万円札の肖像画にまでなってしまったのだから、人材を育成するということは偉業なのだろう。咸臨丸、薩摩屋敷討ち入り事件、勝海舟とのことが頭に残った。2024/09/12
maimai
10
『福翁自伝』の記述で「自分ながらチト物足りぬところ」があったのを補うために、「新たな自伝」として書いたという体の評伝小説。しかしこの「自伝」のぶっ飛んでいるのは、文中に、これを記述中の諭吉だけでなく、いろいろな時代の諭吉が顔を出して、あの時はこうだった、ああだったと言い合いを始めること。そういうことが序文で明かされているのを読んで、これはもうオイラの大好物、とばかりにさっそく買ってきました。で読んでみると、複数の諭吉本人はおろか、「未来」から「作者」なるものまで顔を出してディスカッション。いやいや楽しい。2024/01/18