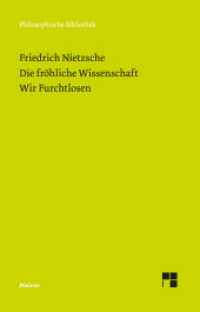内容説明
一見似たような国家が、経済や政治の発展においてまったく異なっているのはなぜか。下巻には坂本龍馬や大久保利通も登場。「ワシントン・ポスト」「エコノミスト」「フィナンシャル・タイムズ」各紙誌の年間ベストブックに選出!『銃・病原菌・鉄』に比肩する新古典。
目次
第9章 後退する発展
第10章 繁栄の広がり
第11章 好循環
第12章 悪循環
第13章 こんにち国家はなぜ衰退するのか
第14章 旧弊を打破する
第15章 繁栄と貧困を理解する
著者等紹介
アセモグル,ダロン[アセモグル,ダロン] [Acemoglu,Daron]
マサチューセッツ工科大学(MIT)エリザベス&ジェイムズ・キリアン記念経済学教授。トルコ出身。英国ヨーク大学卒業後、1992年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で博士号を取得。研究分野は政治経済学、経済発展、経済理論など多岐にわたる。40歳以下の若手経済学者の登竜門とされ、ノーベル経済学賞にもっとも近いと言われるジョン・ベイツ・クラーク賞を2005年に受賞
ロビンソン,ジェイムズ・A.[ロビンソン,ジェイムズA.] [Robinson,James A.]
ハーバード大学デイヴィッド・フローレンス記念政治学教授。英国出身。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)卒業後、1993年にイェール大学で博士号を取得。主たる研究分野は政治経済学と比較政治学、経済発展と政治発展。ラテンアメリカとアフリカの世界的に著名な専門家で、ボツワナ、モーリシャス、シエラレオネ、南アフリカなどで研究活動を行なっている
鬼澤忍[オニザワシノブ]
翻訳家。1963年生まれ。成城大学経済学部経営学科卒。埼玉大学大学院文化科学研究科修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。