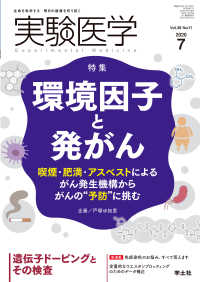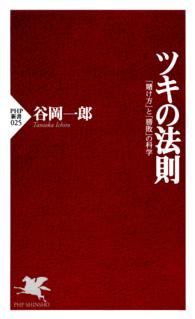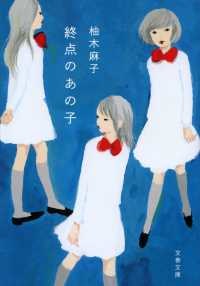内容説明
奴隷の娘フロレンスは、主人の借金の形として北部の農場主に譲り渡された。フロレンスの母が彼女を差し出したのだ。母の真意はどこに?ジェイコブの農場で育ったフロレンスはやがて、自由な黒人の鍛冶屋と激しい恋に落ちるが…。時は十七世紀末。アメリカがまだ未開の植民地だった時代を舞台に、ノーベル賞作家が逞しく生き抜く女性たちの姿を描き上げる、傑作長篇。
著者等紹介
モリスン,トニ[モリスン,トニ][Morrison,Toni]
1931年、オハイオ州生まれ。現代アメリカを代表する小説家。ハワード大学を卒業後、コーネル大学大学院で文学の修士号を取得した。以降、大手出版社ランダムハウスで編集者として働きながら、小説の執筆を続け、1970年に『青い眼がほしい』でデビュー。1973年には第二長篇『スーラ』で全米図書賞の候補となった。1977年の『ソロモンの歌』は全米批評家協会賞、アメリカ芸術院賞受賞に輝き、第五長篇となる1988年の『ビラヴド』(以上すべてハヤカワepi文庫刊)でピュリッツァー賞を受賞した
大社淑子[オオコソヨシコ]
1931年生、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了、早稲田大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sk
3
流麗な文章。クラシック。2019/06/25
livres
1
人種差別の法律さえない頃の、奴隷のお話。初めてみた黒人を、悪魔だと思ってしまうのは、昔だったら、仕方のないことかもしれない。雇い主と使用人たちの、それぞれの立場から見た、世の中や幸せ。底辺にいた白人女性が、結婚を機に使用人も家も手に入れた。でも、幸せを手に入れた訳ではなかったようだ。奴隷は、一生奴隷。奴隷の子も一生奴隷。それにしても、こんなに多くの年月が過ぎて、法律もできて、でも、世界は未だ平等ではないなんて、なんて悲しいことだろう。2011/01/09
しもくわ
1
17世紀末のアメリカという、いまいちイメージが湧かない時代を舞台に、ヒロインの独白とメインとなる登場人物にスポットを当てた章が交互に展開していきます。時代背景の説明なんかぶっとばして問答無用にヒロインの内的世界に飛び込んでいかなきゃいけないハードな小説です。80ページくらいたって、登場人物の立ち位置がやっと分かりましたよ。一読ではとうてい理解できないけど、再読の気力も(いまのところ)ありません。2010/03/08
まろ
0
黒人で、女性で、当時としては弱者中の弱者。それぞれが全く異なる基準で幸せや希望をつかむ姿は感動的。全体像を把握した上で、もう一度読みたい作品です。2012/08/20
ゆき
0
奴隷とゆう概念がどうしても受けつけない。2011/03/30