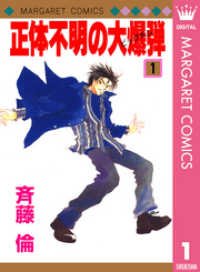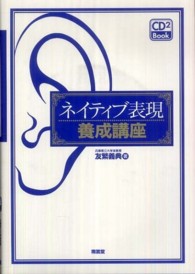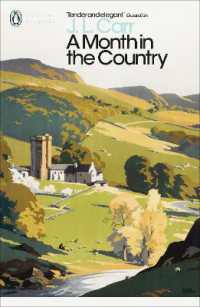内容説明
1920年代の冬のある日、男が若い女を撃ち殺した。女は男の愛人だった。男の妻は女を激しく憎み、柩のなかの死者の顔に切りかかった。しかし、妻は次第に死んだ愛人のことを知りたいと思いはじめる。都会に暮らす男女のなかに生き続ける、時をさかのぼる憧憬と呪縛。過去、現在、未来を自由自在に往来しながら、饒舌な謎の語り手によって、事件の背景が明らかにされていく。ノーベル賞作家が卓越した筆致で描き出す衝撃作。
著者等紹介
モリスン,トニ[モリスン,トニ][Morrison,Toni]
1931年、オハイオ州生まれ。現代アメリカを代表する小説家。ハワード大学を卒業後、コーネル大学大学院で文学の修士号を取得した。以降、大手出版社ランダムハウスで編集者として働きながら、小説の執筆を続け、1970年に『青い眼がほしい』でデビュー。1973年には第二長篇『スーラ』で全米図書賞の候補となった。1977年の『ソロモンの歌』(以上すべてハヤカワ文庫刊)は全米批評家協会賞、アメリカ芸術院賞に輝き、1987年発表の第五長篇『ビラヴド』でピュリッツァー賞を受賞した。1993年にはその多大な文学的功績に対し、アフリカン・アメリカンの女性作家としては初めてのノーベル賞が授与されている
大社淑子[オオコソヨシコ]
1931年生、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了、同大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。