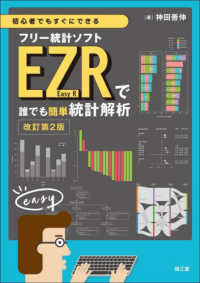内容説明
故国を去り英国に住む悦子は、娘の自殺に直面し、喪失感の中で自らの来し方に想いを馳せる。戦後まもない長崎で、悦子はある母娘に出会った。あてにならぬ男に未来を託そうとする母親と、不気味な幻影に怯える娘は、悦子の不安をかきたてた。だが、あの頃は誰もが傷つき、何とか立ち上がろうと懸命だったのだ。淡く微かな光を求めて生きる人々の姿を端正に描くデビュー作。王立文学協会賞受賞作。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
389
カズオ・イシグロの最初の長編小説。主人公、悦子の回想のスタイルで語られる。ただし、その構造はやや複雑で、イギリスに暮らす現在と、長崎にいた過去とが、その中間部を欠いたままで語られている。この点にこそ、この作品の一番の特質があるのだが、その一方で読者の側には幾分かのフラストレーションが残されることになる。佐知子と万里子のその後も、景子に関わる経緯も不明なままなのだ。2012/04/13
のっち♬
247
敗戦という価値のパラダイムの変化で訪れる過渡期の混乱の中、その犠牲者や微かな希望を棄てない人々の生き方を綴っている。精妙な会話を中心に据えながら、登場人物の心の動きを巧みに表出させ、立場の異なる悦子と佐知子がすれ違う様を見事に描いている。悦子と佐知子、万里子と景子の人生の微妙な重なりも話に奥行きをもたらし、暗い回想の底に流れる悦子の自責の念が独特の色彩を添える。記憶は「思い出すときの事情しだいで、ひどく彩りが変わってしまう」—誰しもが自己の内に物語を創造して心のバランスをとっている。著者らしい薄明な質感。2020/04/28
エドワード
193
第二次世界大戦後の日本の価値観の混乱は、生活の隅々まで及び、人々の心の痛みは深かった。この作品で描かれる、長崎に住む二人の女性<悦子と佐知子>の岐路。佐知子ははっきりと新しい生き方を目指す。悦子は後にイギリスへ渡ることがわかるのだが、性急な佐知子が不安で、迷いの中にいるように見える。勇気、哀しみ、自立心。信じるものは自分しか無い、という強い思い。全体のトーンは「浮世の画家」に近く、旧い価値観から離れられない人々。素早く頭を切り替えて新しい道を歩む人々、呆然と何も出来ない人々、それぞれが愛おしい。2018/11/29
HIRO1970
189
⭐️⭐️⭐️⭐️図書館本。カズオイシグロさんは7冊目。既読「女たちの遠い夏」の改題版でした。イシグロさんの本は私的には難解な部類に入る為、敢えて再読しました。結果的に予習して受けた不得意科目の講義の様に、前回よりもかなり明確にシンプルに伝わって来たのは驚きでした。今の時代もグローバリズムによるパラダイムシフトが世界の果てまで広がっており、一握りの勝者と大勢の敗者を量産する流れが顕著です。かつての繁栄者が自己のアイデンティティーをどうやって保つのかがメインテーマなら英国でのテーマとしてはツボだと思いました。2016/10/16
ケイ
151
随分前に『女たちの遠い夏』として読んだ。改題と知り再読。改めてこの頃のイシグロは良かったなと思う。故郷への回想には、センチメンタリズムよりドライさがぼんやりと感じられ、そのドライさが時代の変遷の不条理さにピタリとはまっている。女の語りにあるのは湿っぽさより諦念だ。「でも、結局、他に大したことがあるわけではないでしょ」結婚し子供を産む女の人生を肯定しない娘への言葉にハッとする。確かに、そういうことかもしれない。日本名が漢字にされていること、女の言葉遣いでイメージが限定されるのが嫌で、原文も読むことにする。2021/08/01
-
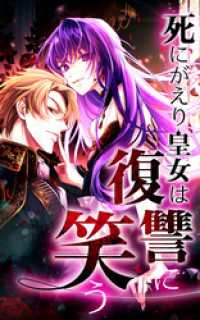
- 電子書籍
- 死にがえり皇女は復讐に笑う 第11話【…