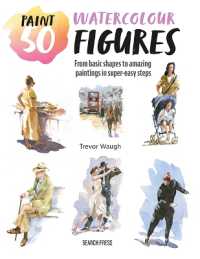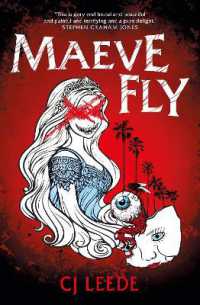出版社内容情報
聴覚障害のある人が多く暮らし、聞こえる聞こえないにかかわらず手話を使って話していたマーサズ・ヴィンヤード島の驚きの実話。
内容説明
ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。遺伝によって耳の不自由な人が数多く生み出されたこの島では、聞こえる聞こえないに関わりなく、誰もがごくふつうに手話を使って話していた。耳の不自由な人も聞こえる人と全く同じように大人になり、結婚し、生計を立てた。障害をもつ者ともたない者の共生―。この理念を丹念なフィールドワークで今によみがえらせた、文化人類学者の報告。
目次
「ほかの人間とまったく同じだった」
2 マーサズ・ヴィンヤード島の歴史
3 ヴィンヤード島の聴覚障害の由来
4 ヴィンヤード島の聴覚障害の遺伝学
5 聴覚障害への適応
6 島でろう者として育つ
7 歴史的にみた聴覚障害
8 「あの人たちにハンディキャップはなかった」
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
90
書店で見つけました。兼々、障害者って何だろうと考えていたので、実に興味深く、とても良いものを読んだと思います。少しでも障害のことに関心がある方には、是非読んでもらいたいと思います。例えば母国語が通じない国で暮らすことになれば、その国の言葉を学ぶように、手話でコミュニケーションをとることが自然な社会。健常者と言うまやかし。もっと社会に関心を持たなければと思います。うまく言えないけれど、勝手に壁を作ることなんて無意味なんだと感じます。2023/01/09
がらくたどん
64
昨日、書店さんから引き取って来た。30年前くらいに築地書館さんから出版されたフィールドワーク記録。図書館本で何度か読んで手元に欲しくても絶版だったのがハヤカワさんから文庫化再版。ありがとう。小島という立地・聾の高い発生率・初期入植者による手話普及により聾者が共同体に溶け込み「聾」がハンデキャップとならずに世代を重ねた歴史を持つ地域の記録は「障がいとは?」「共生とは?」を考える上での授かりもののような実証記録と言える。新たに添えられた解説は現代の視点で、共生とアイデンティティの問題に触れていて興味深い。2022/10/06
サンタマリア
50
共生社会とか道徳的なものはどうでもよかった。ただ、どのような経過で聾の人が多い島になったのか、何故それが続いたのか、島で使われた手話の起源とは、といった疑問点を解き明かすのが面白かった。聾を障害と捉えなかったからこそ、この聾社会が続いたんかなとか意地の悪いことも考えた。人の移動と言葉の変遷の関係性についてもっと知りたい!2023/04/16
くさてる
45
20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害のある人が多く暮らしていた島では、聞こえる聞こえないにかかわらず、誰もがごく普通に手話を使って話していた、その島に関する調査のノンフィクション。島の調査を通して、浮かび上がってきた人々の生き生きとした暮らしの様子に惹かれた。障害ってなんなのか。結局は数なのか、マイノリティかマジョリティかということなんだろうか。専門的な箇所も多いですが、興味深く読みました。2023/07/05
Nobuko Hashimoto
39
かつて、この島では200年以上にわたって遺伝性の聾が高い率で発生していた。島の人たちは小さなころから自然に手話を覚えて使っていた。本書を読むとハンディキャップというものは、社会がつくるものであることがわかる。健常者とそうでない人との境や区別は不変ではない。世界中のさまざまな社会のありようを知ることは、人や社会の可能性を広げることの第一歩になる。関西ウーマンの書評で取り上げました。https://www.kansai-woman.net/Review.php?id=2022102023/02/04
-

- 電子書籍
- ネクロマンサー学園の天才召喚士 1 p…
-
- 洋書
- Maeve Fly