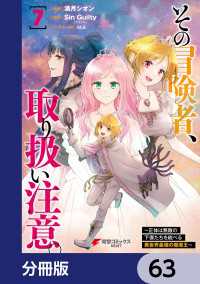出版社内容情報
ホタルの同時発光からスモールワールド現象まで思いもよらぬ現象を数学がつなぐ不思議
内容説明
完璧にシンクロして光る無数のホタルは、どこかに指揮者がいるわけではない。心臓のペースメーカー細胞と同じで、無数の生物・無生物はひとりでにタイミングを合わせることができるのだ。この、同期という現象は、最新のネットワーク科学とも密接にかかわりをもち、そこでは思いもよらぬ別々の現象が、「非線形科学」という橋で結ばれている。数学のもつ驚くべき力を絶妙の比喩を駆使して紹介する、現代数理科学の最前線。
著者等紹介
ストロガッツ,スティーヴン[ストロガッツ,スティーヴン] [Strogatz,Steven]
ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学勤務を経て、現在コーネル大学応用数学科ジェイコブ・グールド・シュルマン教授。専門は非線形力学。カオス、複雑系、同期現象研究の第一人者だが、ダンカン・ワッツとの共著論文で「小さな世界(スモール・ワールド)」理論を提唱、社会ネットワーク論の領域でも話題を呼んだ
蔵本由紀[クラモトヨシキ]
1940年生まれ。1964年京都大学理学部物理学科卒業。京都大学教授、北海道大学COE特任教授などを経て、現在公益財団法人国際高等研究所副所長、京都大学名誉教授。2005年に「同期現象などをめぐる非線形科学の先駆的研究」の業績により朝日賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
紀伊国屋で購入した本本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
67
これまで科学界は「C]の文字で始まる概念を振りかざしてきた。 1960年代のサイバネティックス(cybernetics)、70年代のカタストロフィー理論(catastrophe theory)、80年代にはカオス理論(chaos theory)、90年代には複雑系理論(complexity theory)が次々と登場してきた。 一時は脚光を浴びたが、すぐに限界が見えたりして、まさに科学における流行り廃りを目の当たりにしてきたわけである。2015/03/13
やいっち
65
著者は本書の結びで、「今後の研究で私は、ことあるごとに同期現象へと立ち帰っていくことだろう。それは美しくも奇妙であり、心を激しく揺さぶりもする現象なのだ。同期現象にはある意味で、宗教を彷彿とさせるところがある。(……ホタルが川岸で織り成す明滅の光景への畏敬の念を述べた上で……)同期現象はなぜかわれわれの心の琴線に触れる深遠な現象である。(中略)「自然発生的な秩序の源を突き止めれば、宇宙の謎を解き明かしたことになる」と、人は本能的にわかっているのかもしれない」と書いている。2020/06/18
mura_ユル活動
57
かなり頭が受付けない箇所が大半でした。そんな中でも生活に関わってくるところは一番興味を持って拝読。同期は研究者も未知の領域。生物にとって生殖に関連している。女性の月経などの生理現象も近くの人に影響を受ける。また、心臓のペースメーカー細胞のように自己で動くもの、動きがバラバラであったら、心臓は一体となって動かない。細胞が隣の細胞に影響を受ける、与える。睡眠とも関係、眠れない時間帯に寝ようとしている。この同期が生物だけでなく、無生物にも見られることに驚き。続く→2016/09/13
たかぴ
23
解説では優しいと説明してあったが、正直理解できなかった。同期なのにカオス。スモールワールド。無機質でも同期する。量子から宇宙。こうして単語だけは記載する。分からないことを分かった。量子論が確立した時点でなにか何でもありということが普通にあると思っていたほうがいいのかな。再度読み直したいと思います。ありがとうございました。2020/05/12
オザマチ
17
電気回路と生態学以外で非線形科学に触れたことがなかったので、こんなに様々な分野とつながりがあるのかと驚いた。2021/09/10