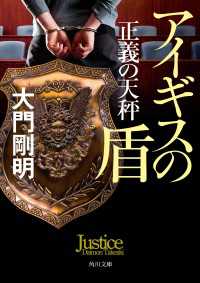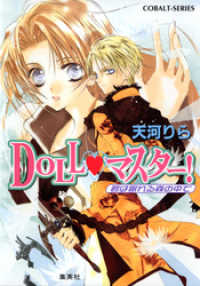出版社内容情報
モンゴルの支配下に置かれた240年。それが、「ロシア」成立の礎となった。
誰もが一度は耳にしたことがある「歴史的事件」と、誰もが疑問を抱く一つの「問い」を軸に、各国史の第一人者が過去と現在をつないで未来を見通す新シリーズ! 第1回配本。 2022年2月に起こったロシアによるウクライナ侵攻。そのとき、プーチンの脳裏に浮かんでいたのは、「全ルーシの君主」イヴァン3世への思いか。二世紀半に及んだモンゴル=タタールの支配――「くびき」がもたらした国家形成の過程を描く。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
111
プーチン大統領のウクライナ侵攻の理由に「タタールのくびき」が鍵になる。10世紀半ばキエフを首都としルーシ国家は、現在のヨーロッパ・ロシア、ウクライナ中・西部、ベラルーシから成っていた。13世紀からおよそ2世紀半モンゴル人による支配下におかれ、タタールのくびきと呼ばれ、1480年ウグラ川での対峙後、ロシア統一国家がタタール人から独立を果たした。その後1654年正式に全ロシアの専制君主と定められた。全ルーシの所有権がロシアにあると1493年大公イヴァンが主張した。その頃からボタンの掛け違えが起こったのだ。2023/05/13
まーくん
96
二世紀半に及ぶモンゴル=タタールのくびきを脱したルーシー国家は基本的にはウラル山脈より西側にモスクワを中心として広がる国で、15世紀末から16世紀初頭に成立したと言われている。これらの国々の中でモスクワが競合諸国を追い落としながら地域の中心となり、イヴァン三世の時代にロシアが成立する。そもそも「タタールのくびき」とはどんなものか?全く理解が及んでいなかった。西方(欧州)の遠征から戻ってきたバトゥ率いるジョチ・ウルス集団はヴォルガ川下流域に居座り都市サライを建設、宗主国としてルーシーを間接支配する。⇒2023/06/14
榊原 香織
61
ロシア史(10~14中心)から、ウクライナ戦へ言及。 平易な書き方ながらスッと理解できないのは、ロシアの形成自体があやふやだからか? リトアニアが巨大で、ウクライナも飲み込んでいた時代があったことがむしろ驚き2023/08/28
aika
50
240年に及ぶ侵略でロシアに傷痕を残したとされるタタールのくびき。モンゴルの支配と片付けられない複雑な経緯についていくのが一苦労でした。モスクワ公国がタタールを利用して周囲を競り落とし勢力を拡大していったこと。そしてタタールで内紛が起き独立のチャンスがきても、ルーシは蜂起せずその支配を認め続けた点は印象深いです。ビサンツとの関係悪化から正教会が庇護を公国に求めたことを機に、政教が強く結ばれたことも初めて知りました。「一般論ではない、個としてのロシア理解がまずは大事」との後書きが、重みをもって胸に響きます。2023/06/04
サアベドラ
39
12世紀後半~16世紀頃まで、ルーシ諸公国がジョチ・ウルス(キプチャク・カン国)の支配下(いわゆる「タタールのくびき」)でいかにしてモスクワを中心とした「ロシア」に再編されていったかを解説するリブレット。2023年刊。プーチンのロシアが主張する「全ルーシの一体性」はあくまでルーシ正教会による理念上の存在であり、イヴァン3世が現在のロシアの原型を作り出した時点では政治的に存在していなかった(キエフを中心とする南西諸公国はリトアニアの支配下にあった)。マイナーな時代・地域の話だがよく噛み砕いて書かれている。2023/12/24