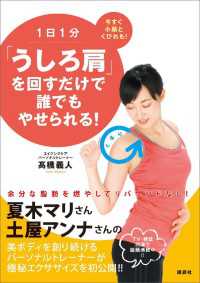出版社内容情報
古代の生活から、日本人の宗教観、文学、芸能のルーツを探る折口の代表作
日本民俗学の嚆矢である柳田国男の影響を受けつつも、祖霊信仰とは異なる「まれびと」や「他界」という独自の概念を提唱し、日本文化研究に大きな足跡を残した折口信夫。本書は国文学や芸能の発生と、神事との深いかかわりを多角的に体系づけようとした彼の主著であるものの、国文学篇1巻、民俗学篇2巻という長大さ、輻輳するテーマなど、初学者にはとっつきにくい難著でもある。生活実感や体験を重んじる調査法や、社会から疎外されてきた芸能者の内包する聖性への気づき、同時代の社会批評的姿勢など、折口ならではの視点に注目して、本書で彼が示そうとした日本文化の基層にアプローチする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
61
その名前は早くに知り、著作も幾つか手許にある折口信夫であるが、彼の言う「まれびと」や「国文学の発生」について、すっと理解することが出来ずにいた。本書で、それらの意味するところやそれらが折口の中でどのような経緯で成立したか、分かり易く端的にまとめられていて、折口古代学への初学者入門の書として相応しい。著者はラストで「他者の文化を知るには、まず自国の文化というものを理解していなくてはなりません。」と述べているが、全くその通りだと思う。グローバル世界を生きるが故に、日本人の魂の拠って来たる所を確かめておきたい。2022/10/20
肉尊
44
日本で最初に『万葉集』の全口語訳を成し遂げた折口信夫の思想を上野教授が紐解いていく!特に掴み所のない「まれびと」とは何者かがよく分かる。折口信夫を研究するにあたり、教授は直観的に捉えることを推める。柳田が祖霊信仰を基礎としたことに対し、折口はまれびとを祖先神と捉えるかは迎え手の判断に委ねると留保している。個人的には意識ではなく無媒介に生の実相を捉えようとしたベルクソンとの親和性を感じざるを得ないが、西洋哲学からの考察はこの本では全くなされていないところが残念。あくまで国文学者からみた折口信夫像という感じ。2022/11/10
井月 奎(いづき けい)
44
折口信夫の代表的著書『古代研究』を孫弟子の上野誠が水先案内をしてくれる。こりゃ読まないわけにはいきません。なるほどなあ、と思わせくれたのが「折口の作品、思考は循環している」との言及です。古代、芸能、万葉集、文芸なども循環して、関係しあって折口のなかにあるというのです。たしかにそうでしょう。そしてそうだからこそ折口の学問、思考は難解なのですが。ほかにも気づきの種をいくつか書いていてくれています。折口信夫を考えるとき、読むときに思い出したい一冊です。2022/10/09
イリエ
20
「おもてなし」から始まったのかあ。「歌」ってそういうこと!? 日本人にとって、神とはなにか? 型から構造に迫っていく感じにゾクッとしました。恩師である柳田國男氏との緊迫のやりとりにも魅了されますね。2022/11/05
ピンガペンギン
13
「100分de名著」3冊目。第1回の部分は今ひとつ納得感に薄かった。第3回「ほかひびと」は古来、各地域にいた神人すなわち宗教者でした。「ほかふ」というのは「祝福する」という意味の動詞に由来している。彼らの保護者であった豪族が大和朝廷によって滅ぼされたり、信仰に変化が生じたりしたときに、一部の宗教者が「村八分のような刑罰によって」共同体から追放された。そして流浪することになった(折口の考えでは)。「蓑笠姿」が彼らの服装。農村の家を廻る。「ナマハゲ」が有名。(というかNHKが大晦日に放送するから有名になった?2023/01/02