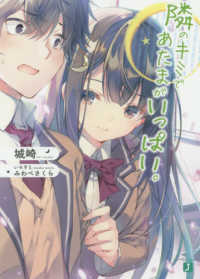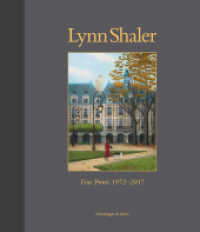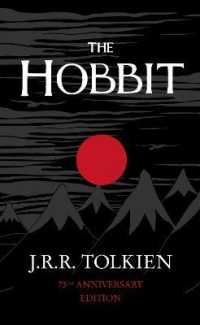感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゃちゃ
108
巻頭に掲げられた、狩野芳崖筆の「悲母観音」。哀しみや苦しみを包み込むような慈愛に満ちた大いなる存在。若松氏は石牟礼さんの文章を引用して、悲母観音の世界はこの作品世界そのものだと指摘し、名著を読み解くための様々な視座を明晰な文章で披瀝する。震えるような想いで読み終えた『苦海浄土』の感動が鮮やかに蘇り、近代文明の恩恵を受けて生きる私たち自身が「もう一人のチッソ」なのではないかという、「終わりなき問い」を投げかけられた。『苦海浄土』と合わせて読むのにお薦めの一冊。石牟礼道子さんの一周忌に、追悼の想いを込めて。2019/02/10
はたっぴ
85
“被害者”が生まれるのは戦争や原発だけではない。公害は近代化が作り出した無差別テロのようなものだ。番組を通して、様々な形で国や企業を相手に立ち向かってきた人々の記録を振り返った。印象的だったのは水俣病患者である緒方正人さんの「国と会社(全て)を許す」という一言。「公害を生み出した人間側の1人として、自分が水俣病にかかったことで、万物を侵略・搾取してきた人間の罪を背負って生きる」という言葉に震えが止まらなかった。艱難辛苦を経験した人の言葉は尊く重い。『苦海浄土』は未だに語り尽くされておらず未完の作品なのだ。2016/09/27
井月 奎(いづき けい)
37
若松英輔は私の目に、実践的な哲学者に見えるのです。その若松は石牟礼から『苦海浄土』を「現代詩の枠組みを超えた新しい『詩』のつもりで書いた」との言葉を得ます。詩は私にとって文芸文学の最高峰の表現方法であるのです。それはこの世の、森羅万象に漂う香気を集めて精製した一滴の香水なのです。詩でこの悲劇を紡ぎだすことは有機水銀に侵されていわれもない殺戮を受けた人々の、また声を奪われ無念の言葉すら発せなかった人々の命に光をあて、意味を見だすのです。予習として読みましたが、時間とお金を使う価値は十分にあります。2016/09/24
ぐうぐう
33
『苦海浄土』三部作を読了後、録画しておいた『100分de名著』の『苦海浄土』の回をまとめて観る。さらにテキストでフォロー。番組は、解説を担当した若松英輔の丁寧な解読が印象的だった(ときに、過剰な装飾的説明には、やや違和感を覚えたりもしたけれど)。ただ、このような丁寧な導きが、『苦海浄土』には必要なのだという意味もよく理解できた。なぜなら、この作品は誤読を誘発する危険性があるからだ。『苦海浄土』は、小説ではないし、かといってルポでもない。(つづく)2016/10/04
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
31
【2回目】苦海浄土・第一部(文庫)本編をフォローするつもりで読んだのだが、「読めた」気がしない。石牟礼さん、若松さんの提起している課題が、「もう一つの時間」に連なっているからだと思う。ぼくは、はじめこの書を「事件の発端」から徐々に真相に迫り、遂には被害者たちが勝利するというようなものと思い込んでいた。しかし、実際にはルポやノンフィクションではなかった。「詩」に近い文学であった。そこには言葉を失った者の代わりに親族などが語った、深い情愛と祈りとがあった。池澤夏樹が「世界文学」とするのも、わからないではない。2018/04/07