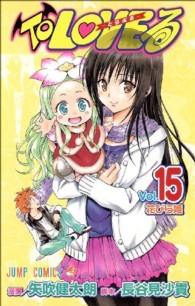内容説明
釈迦の弟子であり、未来の仏であり、さらに救世主である弥勒とは―。京都・広隆寺の半跏思惟の菩薩像で知られる弥勒は、“仏教パンテオン”においては如来としての地位も有する独特の尊格。ヴェーダの宗教、ゾロアスター教などの影響を受けて誕生したミロク=未来の救世主=のあゆみを探り、仏教の東伝とともにユーラシアの各地に広がった祈りの造形の変容をたどる。
目次
序章 半跏思惟像は弥勒か
第1章 弥勒信仰と経典を知る
第2章 弥勒の起源を探る
第3章 初期経典と弥勒像
第4章 大乗仏教のほとけたち―仏教パンテオンの成立
第5章 弥勒と阿弥陀信仰
第6章 伝播の道―弥勒、東へ
第7章 マンダラと弥勒
第8章 日本の弥勒信仰
終章 聖なるものと俗なるもの
著者等紹介
立川武蔵[タチカワムサシ]
国立民族学博物館名誉教授。1942年、名古屋生まれ。名古屋大学文学部卒業。名古屋大学大学院中退後、ハーバード大学大学院留学(Ph.D.)。文学博士(名古屋大学)。専攻は仏教学・インド哲学。名古屋大学文学部教授、国立民族学博物館教授、愛知学院大学文学部教授などを歴任。1991年に「アジア・太平洋賞特別賞」、1997年に「中日文化賞」、2001年に「中村元東方学術賞」受賞。2008年に「紫綬褒章」受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
14
中宮寺半跏思惟像は、弥勒菩薩、即ち釈迦入滅56億年後に衆生救済の為に出現する仏弟子マイトレーヤの修行の姿と一般に言われている。だが本坐像を弥勒像だとするのに根拠は極めて乏しく、朝鮮と我が国でかく信ぜられた一時代があったのみだと記して本書は始まる。仏像が成立した印度北部から世界に広まる中、弥勒像は様々な姿(大仏が多い)をとる。像が多く油容器を手に持つ事から救世神格が窺える事、イラン由来ミトラ神との類似性や我が国身禄行者の入定に論及する。私も大本教の「弥勒の世」を想起する。仏教や宗教に思いを馳せる良書である。2022/07/18
umeko
12
弥勒の来た道は、距離にしても時間にしても遠かった。信仰や図像など、様々な角度からのアプローチが面白かった。それにしても、複雑だった。2015/09/06
nizimasu
5
弥勒というと広隆寺の弥勒菩薩半跏像とかを思い出したりするのだけれど、菩薩でありながら如来的な天上にもいるという摩訶不思議な弥勒の起源を尋ねる旅。その大きなきっかけを著者はミトラ教などの教えに救世主信仰にあるのではないかと考えているようだ。天上にありつつ衆生の信仰の対象にあるというのは、さらには阿弥陀に代表される浄土の信仰と相前後していてそのあたりとの様々な形での融合がはかられていたのではないかというのがとても腑に落ちる。アレキサンダー大王の東征だったりアーリア人の貿易によって文化が行き来した時代ならでは2015/07/17
いけだのどん
1
弥勒菩薩の半跏思惟像は個人的には数ある仏像の中でも最も好きなもの。本書はその起源からどのように伝播してきたのかを辿っている。経典や像としての変遷、時代や地域によって教えの内容の変遷などとことん弥勒にのみ焦点を当てているので(他の宗教の影響なども交えながら)、専門書ではないのだが、用語等少し難しいかもしれない。2017/04/16
इसिबसि तकेसि
1
弥勒の起源を探り、インド、中国、チベット、日本と、その信仰の変遷を辿れます。古くは『リグ・ヴェーダ』の中に表われ、仏典にも初期から登場する弥勒像が大きく変わるのは、紀元前後らしい。その頃に、死後の魂の救済が東西で大きくクローズアップされ、メシア(救世主)という性格が加わる。ミトラを通じて、ゾロアスター教、ローマのミトラス教や原始キリスト教が相互に影響を与えあっているのは興味深いところです。2015/04/03
-
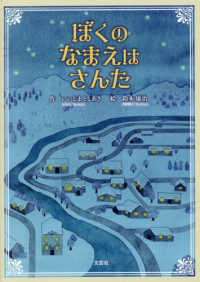
- 和書
- ぼくのなまえはさんた