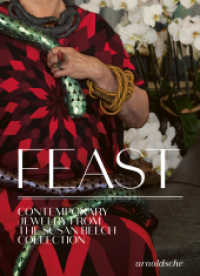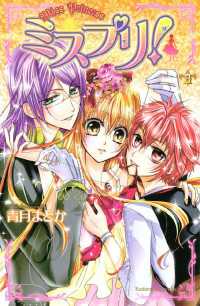内容説明
二〇〇〇年冬、ラオスで出会った「トゥアナオ」(腐った豆)との出会いをきっかけに、著者は納豆の起源を追い求めて、ラオス・タイ・ミャンマー・インド・ネパールでの納豆調査を開始。本書は、約一五年にわたる納豆研究の集大成となる書。糸引きではないセンベイ状・ペースト状など様々な形状、地域によってバラエティに富む発酵方法・調理法など、アジアには私たちの想像を超える納豆文化の多様性が見られた。と同時に、日本から何千キロも離れた地域では、私たちと同じようにご飯と一緒に納豆を食べる人たちもいた。東南アジア大陸部からヒマラヤまでの照葉樹林帯を横断、納豆の起源に迫る!
目次
序章 海外の納豆との出会い
第1章 大豆と日本の納豆
第2章 世界の納豆―その起源をめぐって
第3章 納豆交差点―ラオス
第4章 多様なる調理法―タイ
第5章 納豆の聖地へ―ミャンマー
第6章 ヒマラヤの納豆―インド・ネパール
第7章 納豆の起源を探る
著者等紹介
横山智[ヨコヤマサトシ]
1966年、北海道生まれ。オリンパス光学工業入社、退職後、1992~94年まで青年海外協力隊員としてラオスで活動。筑波大学大学院博士課程地球科学研究科地理学・水文学専攻中退。熊本大学文学部助教授(准教授)等を経て、名古屋大学大学院環境学研究科教授。博士(理学)。専門分野は、地理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
106
「私はなぜ偶然にできた悪臭漂う腐った煮豆食べようとしたのかという点にもっと着目してみたい」と、そこまで言って良いのかい?と、納豆食習慣人の六点は悲しみに暮れたが、そんな事はさておき、ラオス・タイ・ミャンマー・インド・ネパールをめぐる納豆の旅に読者を連れ出してくれる。中共雲南省やインドナガランド地方など調査が欠けている地域は読者をして「そこが大事なんです!」と言わしめるほどの面白さであった。2024/01/27
ばんだねいっぺい
35
野暮なことを言ってしまうとタイトルは「納豆の広がり」がいいんのではと思ったりして。日本人なら「藁」のところを「葉」だったり、平たくしたり、乾燥させてせんべいみたいにしたり、カレーに入れたりといろいろあるなーが面白い。2019/02/03
もえたく
18
高野秀行『幻のアフリカ納豆を追え』に協力者として登場されているアジア納豆研究の第一人者。先日、著者の講演を聞く機会がありお話も面白かったので手に取る。東アジアでは稲藁からよりシダで作った納豆の方がミントの香りで好まれているらしい。2000年にラオスで納豆と出会ったことを契機に、アジアの照葉樹林帯を横断し、納豆の起源を追った記録。文献からフィールドワークまで幅広く、学術的な研究にも関わらず読み易く楽しめました。2024/01/30
ふぇるけん
9
納豆は大豆を納豆菌で発酵させた食品であるが、納豆は日本で見られるようなネバネバと糸を引くものだけでなく、煎餅やクッキー状に乾燥させたものや、味噌のようなものなどさまざま。地域も中国、ラオス、ミャンマー、タイ、ネパールに至るまで広く食べられている。アジアでは乾燥した納豆が中心であるのは、やはり保存を考えてのことと思われる。本書は写真などもたくさんあって、情報量はすごかったが若干文章が固く、ちょっと読むのに疲れた。高野秀行氏の『謎のアジア納豆』の方が文章としては読みやすく、個人的におすすめ。2017/09/23
リョウ
7
納豆といっても地域により製法や形が様々。何よりも、どう見ても腐っているとしか思えない豆を食べてみようと思った先人達の知恵(というか勇気)がすごいと思う。2016/12/17