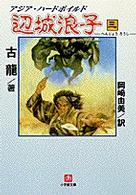内容説明
いま日本の街頭で、そして世界中の広場で、デモの波が広がり、とどまるところを知らない。著者自らオキュパイ・ウォールストリートの現場に飛び、旧来の「社会運動」とも「新しい社会運動」とも違う、「クラウド化する社会運動」の最新展開を徹底調査。あわせて、安保闘争、反公害運動から脱原発デモまで、日本の戦後史をデモという視点から分析することで、時代ごとに激しく変わる日本人と政治の関係を解き明かす。三一一以後の世界で我々が獲得すべき民主主義の姿を探る。
目次
序章 デモとは何か―クラウド化する社会運動
第1章 沸騰する民主主義の現在地―オキュパイ・ウォールストリートを行く
第2章 政治の季節のデモ―大正デモクラシーから一九七〇年代まで
第3章 デモなき消費社会の到来―生活のなかの政治と一九八〇年代
第4章 祝祭としてのデモ―変容する社会運動の一九九〇年代から現在まで
終章 直接民主主義の変貌とわたしたちの政治―三一一以後のデモの姿
著者等紹介
五野井郁夫[ゴノイイクオ]
1979年、東京都生まれ。上智大学法学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了(学術博士)。日本学術振興会特別研究員、立教大学法学部助教を経て、高千穂大学経営学部准教授/国際基督教大学社会科学研究所研究員。専攻は政治学・国際関係論・民主主義論と民主主義思想を研究。世界中のフェスや国際美術展覧会、ストリートから芸術と文化、政治の関係にかんする研究と批評も行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
-
ネコのネット言語学
Purrie…
-
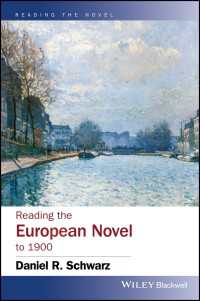
- 洋書電子書籍
-
19世紀以前のヨーロッパ小説を読む