内容説明
なぜ江戸という時代は、人気が高いのか。ゆったりとして見える生活や義理人情にあふれる人間関係が、閉塞感を覚える現代人の郷愁を誘うのか。身分制という軛に縛られながら、身分を序列化するのではなく相対化することを指向した江戸社会。現代の官僚やサラリーマンを彷彿とさせる武士の世界から、都市生活の実相や治安維持システムの実態まで、僅かな格差にも怯える現代社会を見直すために、今に通じる江戸時代の価値観や社会の仕組みを江戸学の第一人者が語り尽くす。
目次
第1章 日本のかたち(切腹と責任;「武士の一分」とは;なぜ平和が続いたのか;日本人と世間)
第2章 武士のかたち(閣僚としての老中;現在に通じる旗本人事;家格意識と抜擢人事;職務のため宴会をする論理;大名の序列と役職に付随した「格」;江戸と地方をつなぐ参勤交代;幕府出向の御三家家臣)
第3章 幕府のかたち(江戸幕府財政を担った勘定奉行所;役得を前提としていた幕府の役職;女性の職場としての江戸城大奥;御台様御用人の破格の出世;江戸時代の国家公務員試験;江戸時代の税制;農民出身者に支えられた幕府の地方行政)
第4章 江戸のかたち(都市生活の原形としての「江戸」;江戸の警察の実体;大店の経営システム;江戸の物流システムと通信ネットワーク;江戸の暮らしぶり;農村の復興をめざした二宮尊徳と大原幽学)
著者等紹介
山本博文[ヤマモトヒロフミ]
1957年、岡山県生まれ。東京大学文学部を卒業後、同大学院を経て、東京大学史料編纂所助手。現在、東京大学史料編纂所教授。文学博士。専門は江戸時代の政治外交史研究および江戸時代の武士研究。1992年、『江戸お留守居役の日記』で第40回日本エッセイスト・クラブ賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroki Nishizumi
takashi1982
PIPI
-
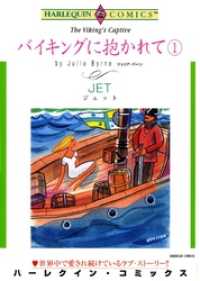
- 電子書籍
- バイキングに抱かれて 1【分冊】 3巻…
-

- 電子書籍
- スマッシュ - 2017年10月号







