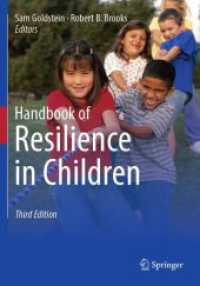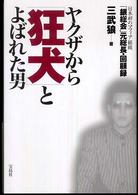内容説明
「サラリー」の語源ともなる塩は、人類に必須の資源である。古代から人は塩を得るため、製塩技術を開発し、交易をしてきた。しかし、ときに塩は文明に災厄を招く物質にもなる。その背景には、この地球上に分布する塩などの物質の偏在を、人間の活動がより強めてしまうという大きな問題があった。塩蔵や発酵食品など世界各地の多様な塩の文化を見ると同時に、シュメール文明の崩壊やカリフォルニア最先端農業の困難、消えるアラル海など、塩のもたらす環境危機の仕組みに迫り、塩の二面性から、人間と自然の過去・現在・未来を見つめる。
目次
第1章 塩とはなにか(塩をとる;塩を使う)
第2章 塩が生かす生命(生命に必要なもの;塩と食文化)
第3章 塩は世界をめぐる(運ばれる塩;森と海の不思議な関係―栄養塩の動き ほか)
第4章 塩と文明の興亡(メソポタミア文明崩壊のなぞ;楼蘭王国は塩で滅んだのか ほか)
第5章 人類は塩とどうつきあうのか(塩とうまくつきあう;塩ははたして有害か ほか)
著者等紹介
佐藤洋一郎[サトウヨウイチロウ]
1952年、和歌山県生まれ。総合地球環境学研究所教授。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。専門は植物遺伝学
渡邉紹裕[ワタナベツギヒロ]
1953年、栃木県生まれ。総合地球環境学研究所教授。京都大学大学院農学研究科単位取得後退学。専門は農業土木学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
8
図書館にて。塩というよりもソーダ工業が目的だったのだが、本書の対象外であった。残念▲めちゃ塩からい塩漬けものから塩を抜くにはどうすれば良いか? 水につけたら良さそうに思えるが、ちゃんと浸透圧に着目しよう。塩漬けものに水をかけたら水を吸って膨らむだけだ。正解はより高濃度な状態にさらすこと。煮物の具材に味が染み込むのは一晩経ってからであって、濃い塩につけたらまず脱水が起きるのだ2024/09/23
a._v._e
1
★★★☆☆2018/01/29
takao
0
塩と文明のような本2016/08/09
きりまん次ゃ郎
0
栄養としての塩、資源としての塩、食文化としての塩、そして農業生産の拡大によって引き起こされる塩害といったさまざまな面における塩のもたらす恩恵とその問題点を軸に、人と塩との切っても切れない関係が書かれている。平易な文章でコンパクトに纏められており非常に読みやすい。2013/12/14
三河武士
0
目黒 2009/10/01
-

- 和書
- 終章石川啄木