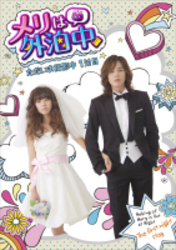内容説明
「消費依存」「ワーカホリック」「バブル現象」「環境破壊」…現代社会の生きづらさはどこからくるのか。出来るかぎり自由であるために選択肢を増やそうと、私たちは貨幣に殺到し、学歴や地位の獲得に駆り立てられる。アダム・スミスから現代の市場理論にまで通底する、“選択の自由”という希望こそが現代社会を呪縛しているのだ。市場(イチバ)で飛び交う創発的コミュニケーションを出発点に、生を希求する人間の無意識下の情動を最大限に生かすことで、時代閉塞を乗り越える道を探究する、著者渾身の市場経済論。
目次
序章 市場の正体―シジョウからイチバへ
第1章 市場経済学の錬金術
第2章 「選択の自由」という牢獄
第3章 近代的自我の神学
第4章 創発とは何か
第5章 生命のダイナミクスを生かす
第6章 「共同体/市場」を超える道
第7章 自己欺瞞の経済的帰結
終章 生きるための経済学―ネクロエコノミーからビオエコノミーへ
著者等紹介
安冨歩[ヤストミアユム]
1963年生まれ。京都大学大学院経済学研究科修士課程修了後、京都大学人文科学研究科助手、名古屋大学情報文化学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科・情報学環助教授を経て、東京大学東洋文化研究所准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





再読本棚
-
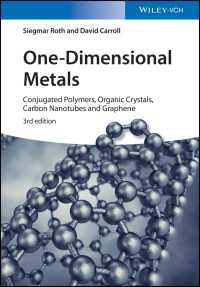
- 洋書電子書籍
- One-Dimensional Met…
-
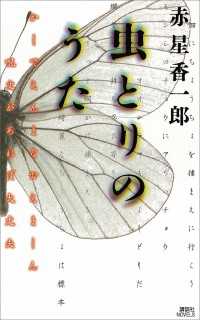
- 電子書籍
- 虫とりのうた 講談社ノベルス